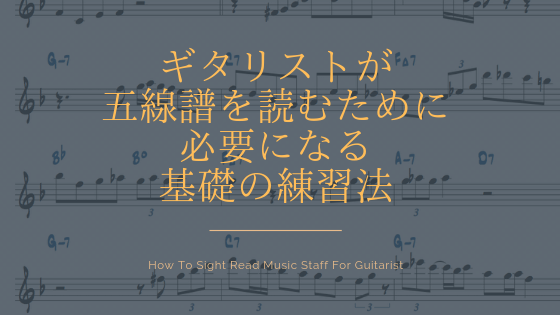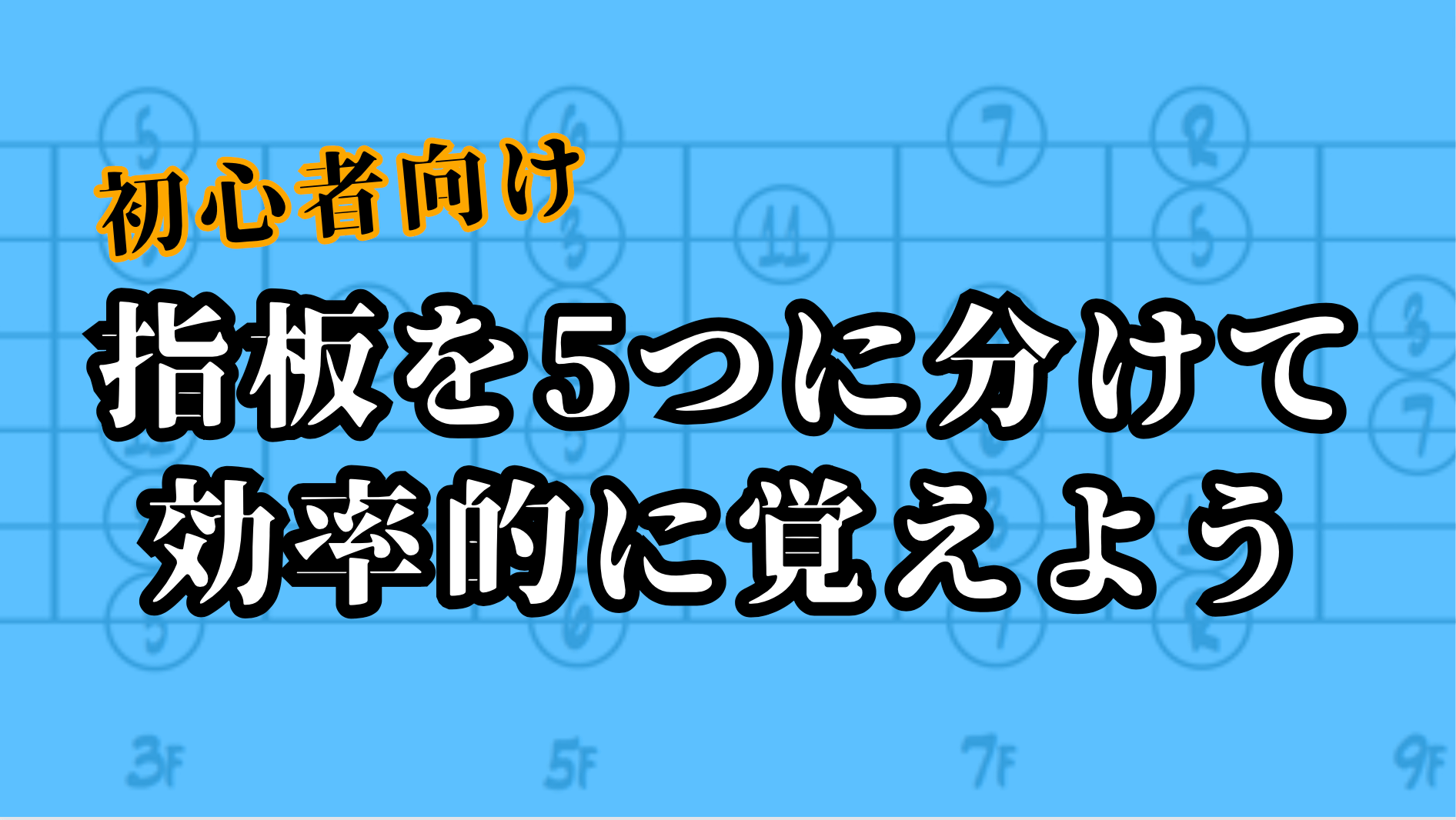五線譜は音楽の共通語です。読めるようにしておくと主に3つの場面で役立ちます。
- リアルブックを使ってジャムセッションするとき
- ライブやレコーディングするとき
- ギター以外の教則本を使うとき
リードシートを初見で読めるくらいの読譜力を持っておくと、困ることはありません。
ここではCメジャースケールを使って五線譜を読むための練習法を紹介していきます。
五線譜を読むための基礎さえ覚えれば、今までタブ譜がないからと諦めていた楽譜も読めるようになり、音楽の楽しみ方も広がっていきます。
ぜひじっくりと取り組んでみてください。
指板上の音の配置を覚える
五線譜をギターで弾くためには2つのステップがあります。
- 五線譜の音符を読むこと
- それをギターに置き換えること
ギターに置き換えるために必須なのが、ギターの指板上の音の配置を覚えることです。
ギター指板上のCメジャースケールの配置
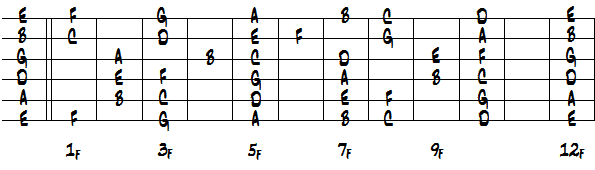
指板上すべてを一度に覚えようとすると大変なので、ポジションを区切って覚えるのが近道です。
jazzguitarstyle.comではポジションを5つに分けて練習していきます。ポジションの分け方や考え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
4〜8フレットの読譜練習
ここでは4〜8フレット(ポジション3)を使って五線譜を読む練習を紹介していきます。
Cメジャースケールの配置
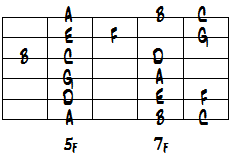
五線上での音域(6弦5フレットA~1弦8フレットC)
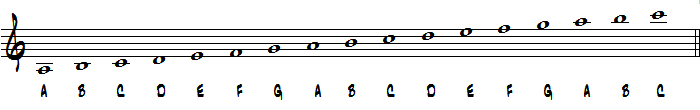
2弦の音
指板上の音の配置は各弦ごとに覚えていきます。どの弦から覚えても構いませんが、ここでは2弦のE、F、Gからはじめてみましょう。
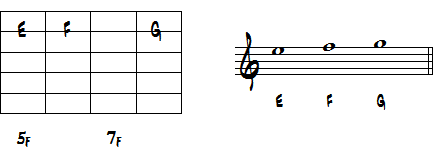
指板上の配置と五線譜での位置を確認したら譜例1を弾いてみてください。
譜例1
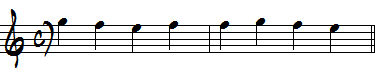
1音ずつ確認しながら弾きます。このとき音名を口に出しながら弾くのも効果的です。慣れてきたら音源のテンポに合わせて弾いてみてください。
3弦の音を追加
3弦はC、Dの2音です。
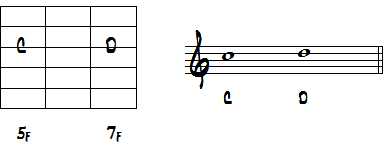
音の位置を確認したら譜例2を弾いてみましょう。
譜例2
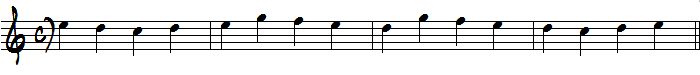
ここでも1音ずつ確認しながら弾いてみてください。
C、D音を覚えたらB音を加えます。3弦4フレット、4弦9フレットのどちらでも弾けるようにしておきましょう。
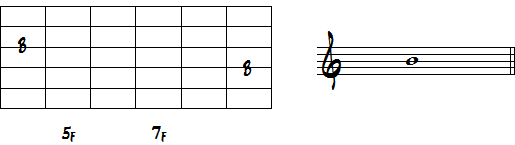
譜例3
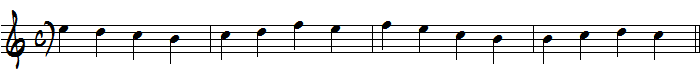
4弦の音を追加
4弦はG、Aです。
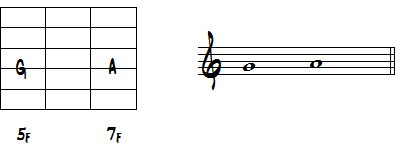
譜例4
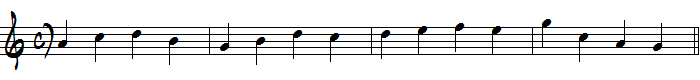
だんだん音域が広くなってくるので、難しければゆっくりなテンポで弾いてみてください。
5弦の音を追加
5弦はD、E、Fです。
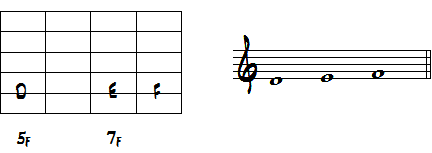
譜例5
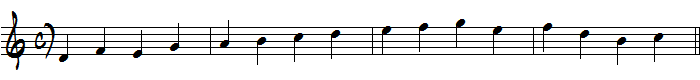
6弦の音を追加
6弦はA、B、Cです。
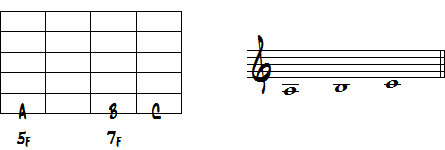
譜例6
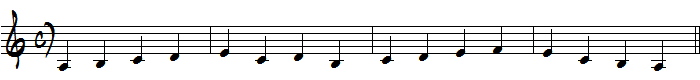
1弦の音を追加
最後に1弦のA、B、Cを加えましょう。
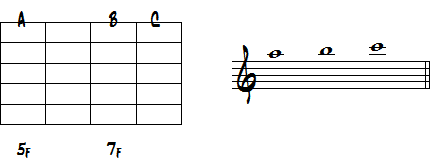
譜例7
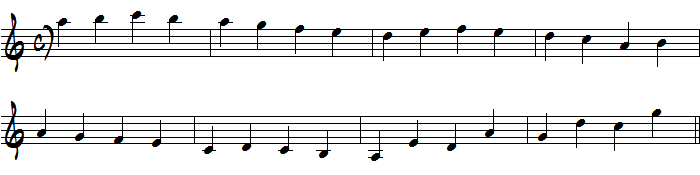
ポジション3の指板上の音の配置と五線譜上での音域を覚えられたら、他のポジションでも同じように練習してみてください。
指板上を「大きな1つのポジション」として見れるようにするのが最終目標です。
リズム付きの譜読み練習
今までは4分音符のみの譜読みでしたが、今度は実践向けにリズム付きの音符を読んでいきましょう。
8分音符を使った譜例1
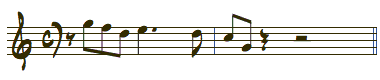
8分音符を使った譜例2
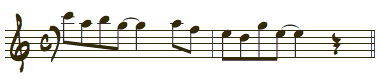
8分音符を使った譜例3
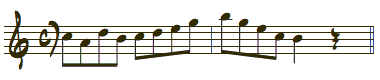
8分音符を使った譜例4
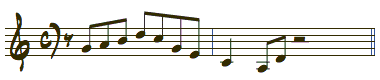
8分音符を使った譜例5
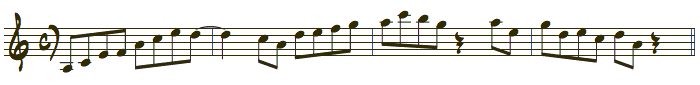
16分音符を使った譜例1
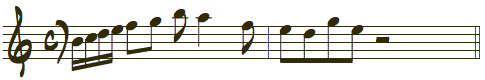
16分音符を使った譜例2
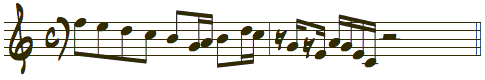
16分音符を使った譜例3
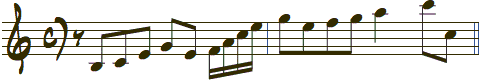
16分音符を使った譜例4
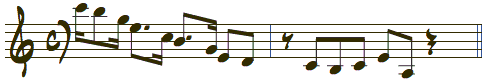
16分音符を使った譜例5
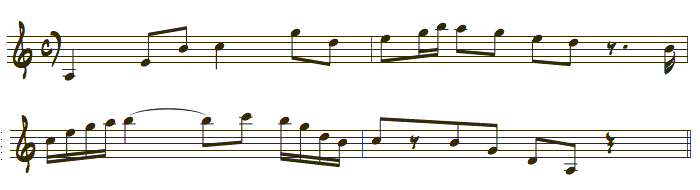
16分音符を初見で弾くのは大変ですが、読んでいるうちに慣れてくるので焦らず取り組んでみてください。
ある程度弾けるようになってきたら、ジャズスタンダードのリードシートを読んでみるのがおすすめです。市販のリアルブックから適当にページを開いて五線譜を弾くと初見の練習になります。
リアルブックはジャズ・スタンダード・バイブルが入手しやすくおすすめです。
臨時記号の譜読み練習
ジャズの楽譜は臨時記号が多く使われるので、しっかりと練習しておきましょう。
ポジション3の1弦から順にシャープとフラットを付けた音を確認していきます。
1弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
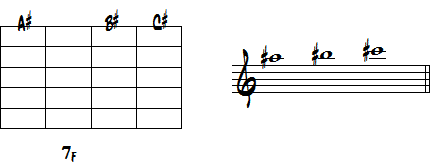
1弦臨時記号#の譜読み練習
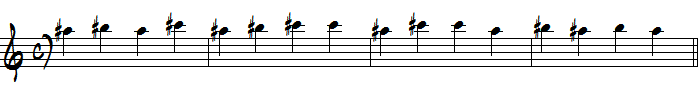
1弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
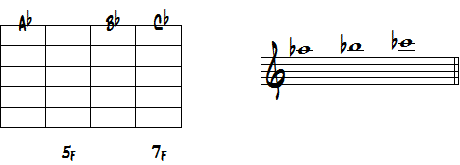
1弦臨時記号bの譜読み練習
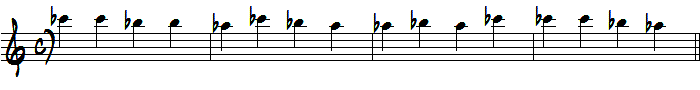
2弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
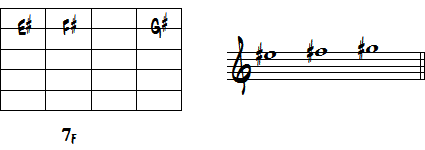
2弦臨時記号#の譜読み練習
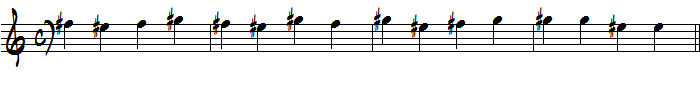
2弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
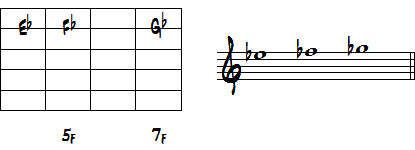
2弦臨時記号bの譜読み練習
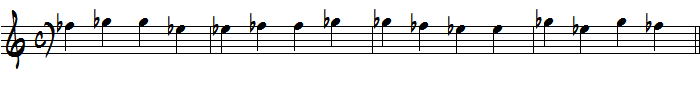
3弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
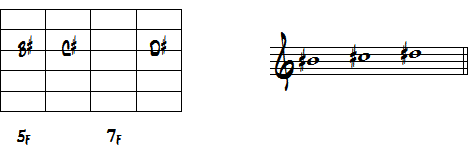
3弦臨時記号#の譜読み練習
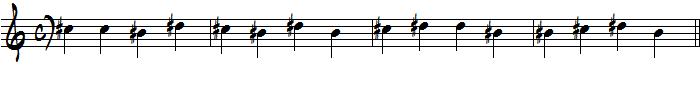
3弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
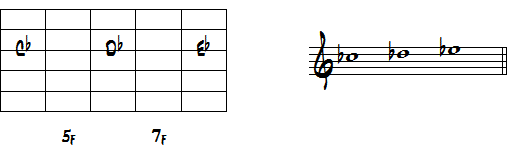
3弦臨時記号bの譜読み練習
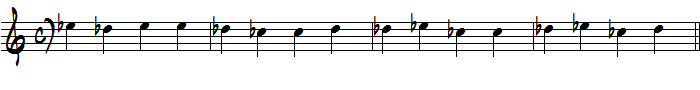
4弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
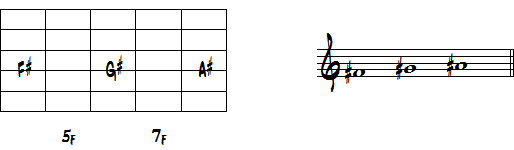
4弦臨時記号#の譜読み練習
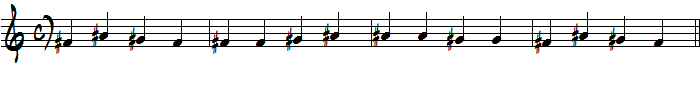
4弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
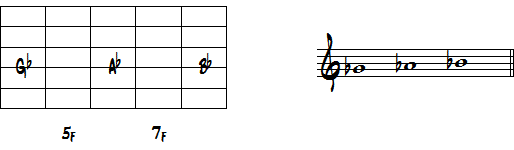
4弦臨時記号bの譜読み練習
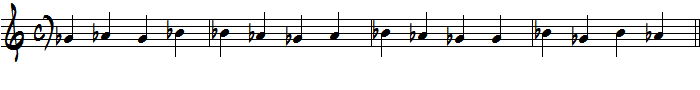
5弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
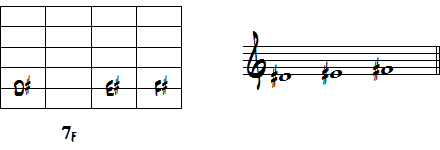
5弦臨時記号#の譜読み練習
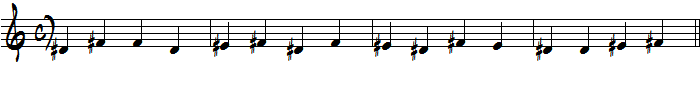
5弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
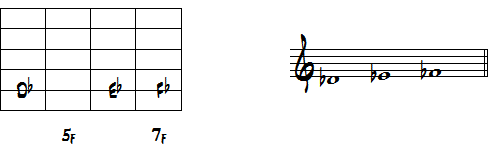
5弦臨時記号bの譜読み練習
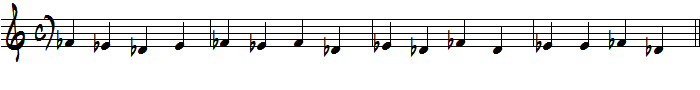
6弦にシャープを付けたときの音の配置と五線譜
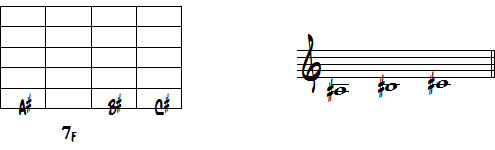
6弦臨時記号#の譜読み練習
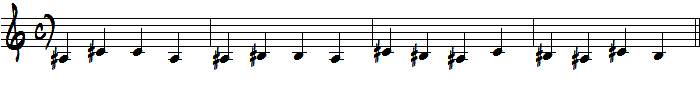
6弦にフラットを付けたときの音の配置と五線譜
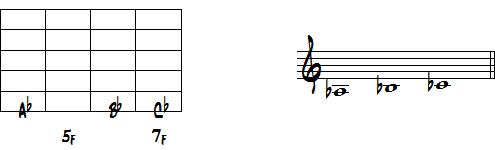
6弦臨時記号bの譜読み練習
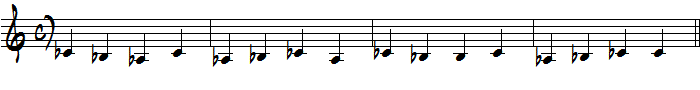
C#とDb、CbとBなどの異名同音もしっかり覚えておくことが大切です。ポジション3の臨時記号を覚えたら、他のポジションでも練習してみてください。
五線譜を読むポイント
五線譜を読むときは、まずテンポ、調号、拍子記号を確認します。
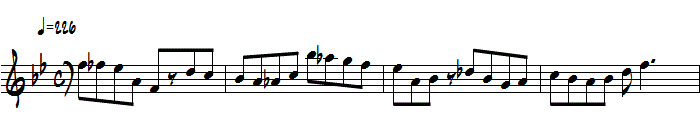
この譜例の場合、テンポは226、調号からBとEが常にフラット、拍子は4分の4拍子になっています。
基本情報が分かったらギターで弾くポジションを決めます。
ポジションの決め方は、その曲で出てくる一番高い音と一番低い音をチェックして、なるべく横移動しないで弾ける場所を探します。
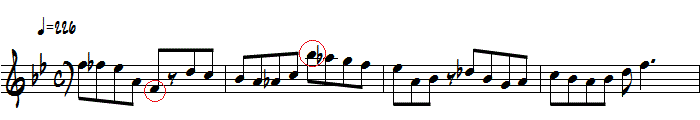
今回の譜面の場合、一番高い音がシb、低い音がファなので、ポジション3で弾けるのが分かります。
実際に弾いてみましょう。
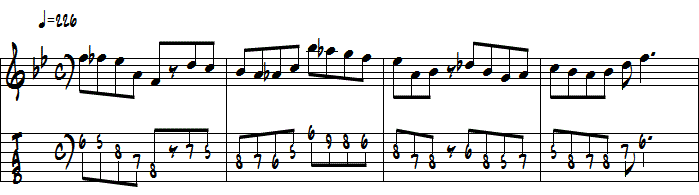
はじめのうちは1つのポジション内で弾ける場所を探すのが簡単です。慣れてくると自分の出したい音のポジションを選べるようになります。
毎日5分でも譜読みの練習を続ければ1年後にはほとんどの五線譜が初見で弾けるようになるはずです。あせらずじっくり取り組んでみてください。
初見で五線譜を読む必要はない?
読譜できると便利な3つの場面
以前は初見(初めて見る楽譜を瞬時に弾くこと)が必須とされる場面が多くありましたが、現代ではその状況も少し変わってきました。
ジャムセッションの場合
ジャムセッションでは、よく知られたジャズスタンダードが中心なので、初見の必要性は高くありません。仮に知らない曲でも、曲を提案した演奏者がメロディを担当するので、五線譜を読むよりもコードネームや曲のサイズ(構成)を把握できることの方が重要になります。
ライブやレコーディングの場合
ライブで演奏する曲は、事前にmp3などで音源が送られてくるので、あらかじめ練習できます。レコーディングも同様です。
1990年代頃までは、まだインターネットが完全に普及せず、やりとりは電話がメイン。そのため代役などの急なライブやレコーディングがあるときは、「明日〜何時にスタジオに来れないか?」といった連絡のみ。当日スタジオに入って楽譜を渡される、というのが普通でした。
現在では急なライブやレコーディングでも、メールなどで「明日演奏する音源と譜面を添付しておく」というように、事前にどんな曲を演奏するのかが分かるようになりました。
ギター以外の教則本
ギター以外の教則本は、1音1音確認しながら弾ければ十分なので、これも初見で弾く必要はありません。
初見よりもポジション選び
実は、楽譜を正確に弾く初見能力よりも、自分にしか出せない音で五線譜を弾く「表現力」の方が重要です。
ギターは同じ音でもポジションによって音色が変わります。「この曲にはこのポジションの響きが合う」など、自分なりのポジションの選び方を意識しておきましょう。
ここで五線譜の読み方の基礎を身につけたら、ぜひ自分なりの読み方、弾き方を研究してみてください。
読譜に関するQ&A
- Qアドリブするときやフレーズを作るときは「移動ド(キーに合わせてドの位置を変える)」ですが、読譜するときは、「固定ド(キーに関わらず実音で考える」でしか読めません。初見で弾くには移動ドで感じれた方がよいですか?
- A
「初見で」となると移動ドはかなり難しいと思います。特に最近のジャズは部分転調が多く、初見で移動ドは**不可能に近いでしょう。そのため、**初見に限っては固定ドで読むのがおすすめです。移動ドで読めるということは、その楽曲を完全に把握している証でもあるので、初見ではなくじっくりと弾けるとき(またはイヤートレーニング)に使うのがよいと思います。
- Q読譜の練習本『バークリー・モダン・メソッド・ギター』がバークリーの授業で使われていると言う噂を耳にしたんですが、どんな授業でどんな感じで使われていたか教えてください。
- A
『バークリー・モダン・メソッド・ギター』は、ギターがメインではない生徒やこれからギターを学ぶ人向けの教本なので、ギターを専攻している授業では使われていませんでした。