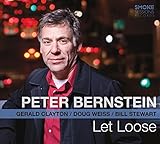ジャズギタリスト、ピーター・バーンスタインが自身のキャリアや音楽への向き合い方を語ったインタビュー(2020年11月20日公開)を、日本語に翻訳しました。
ソニー・ロリンズとの共演エピソードや、ソロ演奏を通して見えてきた発見、そしてエフェクターや音作りに対する独自の考え方まで。
長年にわたって第一線で演奏を続けてきた彼の言葉には、シンプルだけど深い真実が詰まっています。
ジャズギターを愛する人はもちろん、音楽を続けるすべての人に響く内容です。
*本記事は、Samo Šalamon氏の許可を得て日本語に翻訳・編集したものです。
パンデミック下で生まれた『What Comes Next』
—— 新しいアルバムが出るんですよね?
ピーター : 出すつもりはなかったんだけど、たまたまいい機会があってね。2週間で全部終わったよ。スタジオには6時間しかいなかった。
「1曲ずつじっくりやろう」とか「2日かけて録ろう」みたいな感じじゃなくて、「1日でやりきろう」「できるだけ短くしよう」って感じだったんだ。
6月の中旬だったから、みんな長く屋内にいたくなかったんだと思う。全体的に「よし、やろう!」という勢いはあったけど、でも「以前のように戻った」という感じではまったくなかったね。
—— なるほど。
ピーター : でも、とてもいい時間だったよ。
最初は「演奏が鈍っているだろうし、リハーサルなしでうまくいくかな」という不安が大きかった。たとえうまくいったとしても、どこかにぎこちなさとか、久しぶりの緊張感みたいなのがそのまま記録されるんだろうなと思ってたんだ。ライブで何度か演奏したり、しっかりリハーサルを重ねれば、そういう感覚は自然に消えていくんだけどね。
だから「これは結構リスクあるな」って思いつつも、同時に「ギターを持って外に出たい」っていう気持ちが強かったんだ。毎日「今日もどこにも行けないね」ってギターに語りかけてたから。以前はどこへ行くにも一緒だったのに。本当に不思議な気持ちだったよ。
ニューヨークでのレコーディング
—— レコーディングではマスクをしてたんですか?
ピーター : うん。ドラマーはブースの中だから外してたけど、僕とサリヴァンは同じ部屋で演奏したからつけたままだったよ。
ピーター : 当時のニューヨークは、「これだけ大変な思いをしてきたんだから、せめてマスクくらいはしよう」という雰囲気だった。「政府が自由を奪おうとしてる」なんて言う人もいたけど、ニューヨークは早い段階で感染が広がって、本当にひどい状況だったんだ。みんなかなり打ちのめされてたと思う。だから、マスクをつけるのは自然なことだったし、ちょうどマスクが当たり前の時期だったから、外すのはなんだか違う気がしたんだ。
—— 新しい曲もいくつか書いたんですよね?
ピーター : うん、そうだね。「Empty Streets」とか、あの期間にちょうど何曲か書いてたんだ。家にある小さなウーリッツァーでね。そこから2曲くらい生まれて、あと以前に作ってたけどまだ録音していなかった曲もあって、次のチャンスで録ろうと思ってたんだ。それらがうまく一つにまとまった感じだったね。
ピーター : 正直、「自分の曲をその場で初めて演奏してもらうのは悪いな」とも思ったんだ。譜面は事前に送ったけどリハーサルの時間はゼロだったからね。でも、よくあるジャズ・スタンダード・アルバムにしたら、ただ「演奏しました」で終わってしまう気がした。だから、「よし、自分の曲で行こう」と決めたんだ。「とにかく譜面を持っていって試してみよう。うまくいかなかったら、それはそれでいいさ」って感じだったよ。
『What Comes Next』に込めた思い
—— タイトル『What Comes Next』からも感じるように、次に何が待っているのか、という希望のようなものが込められているように思います。
ピーター : そう思ってもらえたなら嬉しいな。僕らは本当に、演奏できることが嬉しかったんだ。曲の中には少し物悲しいものもあるけど、その中にも希望を込めたかったし、少なくとも前向きな雰囲気の曲は入れたかったんだ。
たとえば「Con Alma」はすごくポジティブだし、それからカリプソ調の「Newark News」もね。これはロリンズの曲で、わりと最近の作品なんだ。彼自身は録音していないけど。
ソニー・ロリンズとの関わり
—— どういった経緯でロリンズの曲を録音することになったのですか?
ピーター : 2010年から2012年にかけて彼のバンドで演奏していて、全部で30本くらいギグをやったんだ。最初は代役として4〜5本くらい参加して、そのあと正式に加入することになった。
あるとき、ドラマーが出演できなくなってしまって、新しいドラマーのオーディションがあったんだ。4人のドラマーが順番に来て、1人あたり40分くらい僕たちと演奏した。かなりのプレッシャーだったと思うよ。
そのときロリンズが、この「Newark News」を持ってきたんだ。カリプソのリズムをどう演奏するか試すためにね。それから何度かライブでも演奏したけど、僕はこの曲のメロディが本当に好きでさ。あるときロリンズが手書きの譜面をくれたんだ。「これが君の譜面だよ」って。
—— うわ、それはすごいですね。
ピーター : それで「もし許可がもらえるなら、この曲を録音してみたいな」って思ってね。彼に手紙を書いて、甥のクリフトン・アンダーソンにも「ソニーに録音していいか聞いてくれない?」とお願いした。そしたら数日後に、「もちろんいいよ」と返事をもらったんだ。
“生きる伝説”と共演して
—— ソニーと実際に演奏してみてどうでしたか?
ピーター : 本当に信じられない体験だったよ。何度一緒に演奏しても、「うわ、ソニー・ロリンズがいる!」って心の中で叫んでたよ。歴史上の人物を目の前で見ているような感覚で、まさに“生きる伝説”そのものだった。
ステージだけじゃなく、サウンドチェックの時間でさえ特別だった。ソニーが気まぐれにスタンダードを吹き始めて、それに合わせてセッションが始まるんだ。
あと、ボブ・クランショウと一緒に過ごせたのも大きかった。ソニーはリハのあと自分の時間を大切にする人だったから、むしろボブといる時間のほうが長かったかもしれない。
僕がソニーに会ったのは彼が80歳になる前だったけど、すでに股関節に問題を抱えていたんだ。もともとすごくアクティブな人だったのに、思うように動けなくなっていた。でも彼の世代の人たちって、そういうことを口にしないんだよね。我慢強くて、決して弱音を吐かない。そして何より自分に厳しいんだ。どんな演奏の後でも満足している姿は一度も見たことがない。常に理想を追い続けていたんだと思う。
「俺の足を踏むのを恐れるな」
ピーター : ソニーと過ごした時間は、本当に大きな学びの連続だった。一緒に演奏するとなると、敬意や尊敬の念があって、どうしても遠慮してしまう。でもそれだと、自分がその音楽に何を持ち込めるのか、相手に伝わらないんだ。
それを見抜いたかのように、ソニーが言ってくれた。「俺の足を踏むのを恐れず、思いっきり来い」って。「ただコンピングしてるだけじゃなくて、もっと会話をしよう」ってね。
あるとき、フランスのヴィエンヌのフェスティバルで、「Our Very Own」というちょっと珍しいバラードを演奏したんだ。ソニーが1コーラス吹いて、身体の動きで「次はお前の番だ」って合図をくれたんだ。ベースのボブ・クランショウが「ソニーが下がったら、それがお前のソロの合図だ」って教えてくれてたんだけど、ソニーは完全には止まらなかった。でも僕も止まらず、結局2コーラス丸々一緒に弾いたんだ。
そしたら終わったあと、ソニーが「それだよ。それが俺の言ってたことだ」って。つまり、どんなに敬意を持っていても臆せず一緒に混ざれということだった。僕は「あなたは神様みたいな存在で、自分はそんな立場じゃ…」って思っていたけど、ソニーは「ぶつかり合ってこそ会話になる」と教えてくれた。
その瞬間、気づいたんだ。本当に偉大な人の前では、恐れずに向かうことこそが、いちばんの敬意なんだって。この経験が僕にとって最大のレッスンだった。
勇気と確信
ピーター : それ以来、人と演奏するときの気持ちが変わった。「ソニー・ロリンズとやったから怖いものなし」って意味じゃなくて、「誰とでも対等に向き合える」っていうポジティブな感覚になったんだ。
音楽的にわからない状況や、自分の理解を超える演奏に出会っても、「今はまだ理解できない会話なんだな」って受け止められるようになった。一方で、曲を理解し、何が起こっているか分かっていて、自分のアイデアがあるなら、あとは迷わずやるだけなんだ。
自分の選択を疑ったり、「あの人の前だから…」なんて考える必要はない。強い人と一緒に演奏すると、自分の演奏にどれだけ確信を持てているかが試されるんだ。その教訓は、「自分を信じること」。たとえまだ信じきれていなくても、それを表に出しちゃいけない。とにかく、確信を持っているようにプレイする。結局、音楽って「選択」と「その選択を信じる勇気」なんだ。
大胆さの源は、身体だった
ピーター : ソニーはまさに「勇気の人」なんだ。いや、「大胆さ」 と言ったほうが近いかな。多くの曲はシンプルな調性で、たとえば「Newark News」は I–IV–V、せいぜいVIくらいで完結してるような構造なんだけど、ソニーはその中であらゆるキーを自在に吹くんだ。しかもそれが自然なんだよ。
「そんな発想ある?」って思うようなフレーズが次々出てくる。しかも、それがすべてメロディから生まれていて、曲の核とつながっているんだ。彼にとって音楽は「シンプルなものを無限に変奏する遊び」だった。
そして、その“遊び”の根底にあるのが、身体と音楽の一体化。ソニーはリズムを演奏していたんじゃなくて、リズムそのものになっていたんだ。身体が動くたびに音が生まれ、音が鳴るたびに身体が反応する。単に拍の終わりにフレーズを置くとか、機械的に鳴らすとか、そういう理屈じゃない。彼の演奏は、全身で音を感じ取り、動きながら鳴らすことだった。
だから、ソニーの演奏は常に生きている音だった。どんなに身体が痛んでいても、彼のリズムは全身にみなぎっていた。リズムが身体の中に宿り、身体がそのまま楽器になっていたんだ。
大空間で「親密な音楽」を鳴らす挑戦
—— 僕の愛聴盤のひとつが、ソニーロリンズとジムホールが共演した『The Bridge』なんです。
ピーター : 僕もだよ。あれは本当に特別なアルバムだ。
—— ソニーと共演したとき、『The Bridge』を意識しましたか?
ピーター : もちろん、いつも頭にあったよ。しかもボブ・クランショウも一緒だったからね。「1962年の『The Bridge』を作ったあの二人と、今同じステージにいるのか」って思うと、その重みは相当だったね。でも、演奏のアプローチはまったく違っていた。
僕らのサウンドはもっと大きくて、スケールが違った。大きなステージで繊細な音楽をどう表現するか、常に考えさせられたよ。だって、ほとんどロックコンサートみたいな環境だったからね。
ベースはエレキが中心で、ときどきスティックベースも使っていたけど、全体の音量はものすごかった。ドラムも力強く、さらにコンガのプレイヤーも加わって、音の世界がどんどん広がっていった。まるで音の壁の中で、自分の声をどう響かせるかを探っている感覚だったよ。
—— アンプの音量も上げたのですか?
ピーター : できるだけ抑えようとはしたけど、それでも全体的にはかなり大きな音だった。フランスのヴィエンヌみたいな野外フェスでは、広い空間を満たすサウンドが必要だった。以前、ダイアナ・クラールとも共演したモントレー・フェスティバルなんて、8,000人くらい入るんだ。
ピーター : もちろん小さい会場でもやったよ。たとえばアンティーブ・ジャズ・フェスティバル。観客が何千人も並ぶ場所じゃなくて、もっとカジュアルでリラックスした雰囲気だったんだ。そういう会場では、より親密な空気を感じたね。でも、それでもソニーの音は大きかった。マイクをサックスのベルにぴったりつけてたからね。
音作りの違い
ピーター : 『The Bridge』は独特の親密さがあるよね。ジム・ホールのギターもそんなに大きな音じゃなくて、ただ美しくて、繊細なバランスがある。ラルフ・グリーソンのテレビ番組で演奏してる映像では、メンバーが近い距離で向き合って、耳を傾けあいながら完璧に溶け合ってる。おそらくベースにもアンプなんて使ってなかったと思う。
つまり、あの時代は音の作り方がまるで違うんだ。でもソニーはそれをよく理解しいた。今はもっと大きな空間で、何千人もの観客に向けて演奏しているっていうことを。だから音楽の中に“親密さ”があっても、同時に“広く響かせる意識”が常にあったんだ。
—— なるほど。
ピーター : 僕自身は、ああいうスケール感に完全に慣れたとは言えないけど、ダイアナ・クラールやジョシュア・レッドマンと一緒に大きなホールで演奏して、少しずつ感覚を掴んでいった。
でも正直言うと、観客が10人でも1万人でも、やることは同じなんだ。いつも自分の世界にいて、周りのミュージシャンと音でコミュニケーションを取ることに集中している。もちろん観客の存在は大好きだし、たくさんの人の前で演奏するのも楽しいよ。
—— よくわかります。
ピーター : でも僕はエンターテイナーではないんだ。サミー・デイヴィス・ジュニアみたいな“魅せる”タイプではなくて、どちらかといえば“聴かせる”タイプなんだと思う。
でもソニーは本当にすごかった。彼は何も意識していないのに、自然とカリスマ性が溢れていたんだ。しかも、それをちゃんと外に向けて発していた。彼の演奏には内向的な要素なんて一切なくて、完全に外へ、聴衆へ、世界へ向かっていたんだ。
「それは君が決めることだ」
ピーター : すごく印象に残ってる出来事があってね。さっき話した別のドラマーが来てたリハーサルのときだったと思う。「Newark News」をやってたんだけど、どうもグルーヴしなくて、ソニーが明らかに不機嫌だった。
ドラマーたちは頑張ってたけど、ソニーが求めてるものが出てこない。いろいろアドバイスしても、なかなか噛み合わなかった。でもある瞬間、テンポを変えたのか何かがハマって、突然グルーヴし始めたんだ。そのときソニーがピタッと止まって、「そう、それだ! 今の感じだよ! それがグルーヴってもんだ!」って言ったんだ。ドラマーはすごく喜んでたよ。
そしてその勢いのまま、こう聞いたんだ。「ロリンズさん、こういうカリプソの曲では、スネアはオープンにしたほうがいいですか?クローズですか?」って。どういうサウンドを出せばいいのか知りたいっていうごく自然な質問だった。でもその瞬間、ソニーが20秒くらい黙り込んだんだ。ちょうどいい雰囲気になった直後の沈黙で、僕は思わず「やばい…」と思った。
やがて口を開いたソニーはこう言ったんだ。「それは君が決めることだ。音楽は選択の連続なんだ。君は音楽のためにここにいる。そして、演奏の中で自分の判断をしていくためにいるんだ」って。
僕の意訳になるけど、彼の言いたかったことは、「君はいま、決断を下す側にいる。そしてそれは、何よりも恵まれた立場なんだ」と。
自由を裏切るな:即興に伴う「責任」
ピーター : ソニーは続けてこう言ったんだ。「世界中には交響楽団がたくさんあって、何千人もの素晴らしいミュージシャンがいる。彼らは素晴らしい技術を持っているけど、指揮者に従って、譜面に書かれたことを演奏しなければならない。でも僕らは違う。僕らは即興してる。自分で何を弾くか決めてるんだ。つまり、それは特権なんだ。自由を持ってるということなんだよ。」
「でもね、その自由には前提がある。音楽のために演奏することだ。自由だからといって好き勝手にやれば、それは自由を裏切ることになる。逆に正しくやらなきゃと思いすぎると、今度はロボットのようになってしまう。大事なのは自分で選ぶことなんだ。音楽の中に深く入り込んでいれば、音楽が何をすべきか教えてくれる。自分の感覚を信じるんだ。信じた上で、勇気を持って決断し、一度決めたらそれを貫く。スネアを開けるか閉じるかなんていう伝統的なルールはどうでもいい。大事なのは、音楽を感じて、その音楽のために弾くことだ。」
その言葉を聞いて、僕の考え方が完全に変わったんだ。それまでプロとして演奏して、たくさんの人と共演して、レコードも作ってきたけど、即興って「特権」なんだって考えたことは一度もなかった。即興できない人がどれだけ多いかを考えると、自分がやってることの意味が全く違って見えてきた。
もちろん、僕にも素晴らしい先生がいたよ。ジム・ホールのような人、そしてレコードを通して教えてくれた先生たち。彼らの音がいつも教えてくれたんだ。「即興はただ弾くことじゃない。ちゃんと意味を持たせて物語を作れ」って。
最高のソロには必ず物語がある。構成や語彙、フレーズは他のソロと似ている部分もあるけど、でもそれはひとつの物語として成立している。演奏者は語彙を持っていて、即興しているけど、その中に”瞬間の決断”があるんだ。
だから、ただフレーズを並べるんじゃなくて、即興で「小さな歌」を作るのが大事なんだ。それをソニーが“特権”として語ってくれたのが衝撃だった。「既に書かれた美しい物語を何度も朗読する」のではなく、“いまこの瞬間に物語を作る”ことこそが、僕らに与えられた特権なんだよ。
—— 本当にそうですね。
ピーター : たとえそれが1日だけのリハーサルだったとしても、1年半の活動で他に何も得られなかったとしても、この言葉だけで十分だったと思う。「ああ、そうか。そういうことなんだ」って。
“特権”を与えられて、自分の思うように演奏できる“自由”を持っているということは、同時にそれが「挑戦」でもあるんだ。つまり、扱う“題材”をちゃんと理解していなきゃいけない。曲を学ぶ。音楽を学び、もっと深く掘り下げる。自分の演奏を“飾り立てる”ことよりも、音楽そのものを知ることに集中するんだ。
—— 内容そのものに、ということですね。
ピーター : そう、曲の“中身”を知ること。音楽のために弾く。曲を理解して、その曲の中から弾く。つまり、即興っていうのはすごく重いものなんだ。自由や力というのは、それだけ大きな責任を伴う。まるで「大いなる力には、大いなる責任が伴う」みたいにね。だからこそ、即興する人間は「誰かに聴かれてるから、かっこいいフレーズを弾かなきゃ」なんて思うのではなく、この責任をちゃんと意識しなきゃいけないんだ。
名ソロの秘密「Pantomime」
—— “ソロの物語性”という点で言うと、ジョシュア・レッドマンの『Freedom in the Groove』に入っている「Pantomime」でのソロが素晴らしくて。もちろん即興なんでしょうけど、まるで作曲されたように聴こえます。
—— 間の取り方やインターバルの使い方が本当に絶妙で、弾きすぎないバランスも完璧なんですよね。どうやってそういう感覚を身につけたんですか?
ピーター : うーん、どうだろう。あのとき何を考えていたかまでは覚えていないんだけど、基本的には「曲が自分に何を与えてくれるか」を見るようにしているんだ。
僕にとって即興というのは、「その瞬間にあるもので最善を尽くすこと」なんだ。たとえば——「しまった、鍵をなくした!」という状況で、「どうやって家に入ろう?」と考える。そこにハシゴがあれば、「よし、これを使おう」ってなる。つまり、“今あるものでどうするか”を考える。それが即興なんだ。
これを音楽に置き換えると、「曲そのものを使う」ってことになる。曲を理解して、そこから何かを見つけ、自分にしかできない演奏をする。ただ、続けていくうちに「この曲ではこう弾く」と決めつけてしまう危険もある。自分の“お決まり”に閉じこもるのは怖いことだ。だから、そうならないように気をつけているよ。
大事なのは、「今、自分が持っているもので、曲全体をどう見るか」なんだ。コード進行を追うだけじゃなくて、メロディやインターバル、曲の感情まで見渡す。だって辞書のどこを探しても、「即興とはスケールやアルペジオをコードに当てはめること」なんて書いてないだろ?
そんな定義を作ったのは、きっとどこかの教育機関の誰かだよ(笑)。でも実際の即興はもっと深いものなんだ。もし曲の中にたったひとつでも遊べる要素があるなら、それを掘り下げてみるといい。そうすれば、自分の弾く音がその曲の中で意味を持つようになる。逆に、どんなに上手いフレーズでも、曲と関係なければそれは“独り言”みたいなもの。説得力なんて生まれない。
だから僕は、どんな曲でも、人のオリジナル曲でも「そこに何があるのか」を見て、それをもとに何かを作り出すようにしているんだ。
ジョシュア・レッドマン・バンドでの“葛藤”と“成長
—— 「パントマイム」を聴いたのは、僕がジャズを始めたころで1997年のことでした。「なんて最高のギタープレイなんだ!」って思ったんです。
ピーター : ありがとう。ロック・バラードみたいな曲だよね?あのレコーディングのとき、実はまだ今のギターを持ってなかったんだ。手に入れたのは翌年の1998年なんだ。
—— えっ、そうだったんですか?
ピーター : そう。当時はL-5を弾いてたんだ。それまで使ってたES-175よりもずっと大きくて、慣れるのに苦労した。まるでモンスターみたいなギターだったよ。ES-175では何枚かレコードを作ったんだけど、L-5は完全に上位モデル。サスティンも長く、鳴りも強い。ネックの角度も深くてテンションが高いから、とにかく弾くのが大変だった。
だから、ジョシュと演奏してたときは、彼らがあんなに滑らかに演奏する中で、自分だけが泥の中でもがいてるような気分だったんだ。「なんでこんなに流れに乗れないんだろう」ってね。
ギター本来の音をつかむまで
ピーター : 今のギターを手に入れてからも、“慣れの壁”はかなり高かった。それまでのどんなギターより倍音が豊かで、初めて「音をどうコントロールするか」を真剣に考えさせられたんだ。ピアニストが普段は小さなアップライトで練習していて、いざライブで12フィートのスタインウェイを弾くような感じだね(笑)。「うわ、こんなに音が広がるのか!これは手に負えないぞ!」って。
そのとき、自分の奏法の甘さや不正確さが全部見えた。まるで、鏡で顔を見たときに、明るい照明に照らされて、細かいシワまでくっきり見えるようなものさ。
このギターを手にしてから数年かけて、ようやく「こうやって音を出すんだな」って感覚が少しずつ掴めてきた。今でも修行中だけどね。年齢を重ねるにつれて分かるのは、テクニックを伸ばすことと同じくらい、自分の限界の中でどう音楽を作るかを学ぶことが大切だということ。
生徒にもよく言うんだ。「自分の得意なことがあるなら、それを活かしなさい」って。もちろん、それを起点にして少しずつ広げていく努力も大事だけど、無理に全部をやろうとするよりも、自分にとって気持ちよく弾けることを磨くほうがいい。だって、弾いてて気持ちいいものは、聴く人にもそのまま気持ちよく響くからね。でも多くのギタリストは自分を追い込みすぎるんだ。とにかく速く弾こうとして、まるでチャーリー・パーカーみたいに弾こうとする。そのフレーズが本当に自分の耳に聴こえているならいいけど、そうでなければ、ただの模倣にすぎない。
結局のところ、今の自分にあるものでどうするかなんだ。たとえ限られた色鉛筆しかなくても、美しい絵は描ける。すべての色が揃っていなくてもいい。今ある色で描けばいい。そして、最後に大事なのは“タッチ”なんだ。弦にどう触れて、どんな音を引き出すか。いい楽器を手に入れるのも大切だけど、それ以上に、その楽器の力を引き出せるように努力しなきゃいけない。
グルーヴとストレートアヘッドの狭間で
ピーター : ジョシュアのバンドには1995年から97年まで参加してたけど、あの頃の僕は本当に苦労してた(笑)。新しいギターに慣れてなかったし、ツアーに出るのも初めてだった。フェスティバルを1か月かけて回るようなツアーでは、毎晩同じメンバーと同じ曲を演奏して、自分の演奏とも向き合う日々。本当に“深い経験”だったよ。続けること、一貫性を保つこと、そしてツアー中に音楽を新鮮に保ち続けること。その難しさと、そこから得られる学びの大きさを痛感したんだ。
—— あのバンドは本当に凄かったですよね。
ピーター : ツアー自体はすごく楽しかったよ。1996年の終わりから翌年の夏前までは、フェスティバルを中心に各地を回った。全部がフェスってわけじゃなくて、規模が小さい会場も多かった。そんなに長い期間じゃなかったけどね。
ヨーロッパやアメリカでのパスツアーも何度かあったよ。朝、バスを降りてホテルにチェックインして休んで、夜のギグが終わったらまたバスに乗ってそのまま寝る。あれは最高だったな。移動時間をムダにしないって意味でもいい方法だったし、いろんな場所を見られて、本当にいい経験だった。
当時はまだ、ありがたみを感じる余裕なんてなかったけど、それでも楽しかったし、とにかく音楽を学んで、ついていこうと必死だった。だって、僕が入る前からもう彼らはバンドとして出来上がっていて、すでにヴィレッジ・ヴァンガードでライブ盤も出してたからね。僕は後からそこに加わった立場だったんだ。
ジョシュはギターを入れることで、サウンドをより現代的にしたかったんだと思う。いわゆるジャズ・クインテットっぽさを減らしたかったんじゃないかな。
—— もっとグルーヴィーにした感じですよね。
ピーター : そうそう。ジョシュはその方向を意識して曲を書いてたと思う。でも、たぶん僕は彼が望んでたことを完全にはできてなかったんじゃないかな。というのも、バンドの中で僕がいちばんストレートアヘッド寄りだったんだ。僕はただ、グルーヴのある曲やブルースを弾いたりしただけだったから、そこに“新しい何か”を吹き込めていたかというと、自信はないんだ。
—— なるほど。
ピーター : まあ間違ってるかもしれないけどね。ジョシュから「がっかりした」なんて言われたことは一度もない。でも今になって振り返ると、彼がどんな音を求めてたのか、なんとなく分かる気がするんだ。たぶんジョシュはジャズ・クインテット的な響きから抜け出したかったんだと思う。もしそれを求めていたら、トランペットを入れればよかったわけで。そうじゃなくて、ギターを入れることで、音楽をもっと現代的でグルーヴのある方向に広げたかったんじゃないかな。でも僕は、ストレートアヘッドなプレイを貫いていたんだ。
—— そう聞くと、ますますあのアルバムが特別に感じます。
ピーター : そう言ってもらえるのはうれしいよ。あれはジョシュの作曲が、アルバムのサウンドそのものを作ってるんだ。
アルバム『Signs of Life』とその裏側
—— ブラッド・メルドー、クリスチャン・マクブライド、グレゴリー・ハッチンソンと一緒に録音した『Signs of Life』は、どういうきっかけで始まったんですか?
ピーター : あれはね、僕の最初のギター、ES-175を使ってた頃の録音なんだ。
—— そのギターは今も持ってるんですか?
ピーター : うん、今も持ってるよ。L-5はもう手放したけどね。当時はブラッドとよく演奏していて、ジミー・コブとも一緒にやってたんだ。いろんなグループやリズム・セクションで演奏したけど、僕の最初のアルバム『Somethin’s Burnin’』はブラッド、ジョン・ウェバー、そしてジミー・コブと一緒だったんだ。それでカルテットのサウンドが気に入って、新しい曲もいくつかあったし、「次のアルバムもこの形でやってみよう」と思ったんだ。
あるとき、グレッグとクリスチャンが一緒に演奏してるのを聴いて、「なんてすごいリズム・セクションだ!」って思ってね。グレッグとは以前からの知り合いだったし、クリスチャンとも少し面識があったから、「このメンバーでやってみよう」と声をかけたんだ。
実は、あのカルテットはもともと活動してたバンドじゃないんだよ。リハーサルを1回やって、その翌日に録音したんだ。ライブは一度もやってない。
—— えっ、本当に?
ピーター : うん、一度も。
『Signs Live!』誕生の舞台裏
—— 再結成した『Signs Live!』のときはどうだったんですか?
ピーター : あのときはDizzy’s Clubで3日間だけ演奏したんだ。そのうち、最後の2日間を録音した。もともと「アルバムにしよう」と思って録音したわけじゃなくて、最後の夜の演奏を聴いたレーベルが「これを出そう」と言い出したんだ。
—— 1曲目の“Blues for Bulgarian”からすごいですよね。17分もあって、まさにライブの勢いを感じました。
ピーター : 実は、「これはアルバムにはしないほうがいい」って思ってたんだよ。でもレーベル側が「あの夜の演奏をそのまま出そう。2枚組にすればほぼ全部収録できるし、いい作品になるよ」って言ってきてね。最初は「3枚組にしよう」なんて話まで出てたけど、「それは無謀だって!3枚組なんてクレイジーだよ!」って(笑)。結局2枚組になって、ほとんど両セットをまるごと収録することになったんだ。
僕はむしろ、スタジオに入って新しい曲を録ったほうがいいんじゃないかと思ってたんだけどね。
—— そうだったんですね。
ピーター : ライブ録音は聴き直したりもしなかったよ。2日目の夜を使うって言うから、「まぁ、あの夜のほうが良かった気がするし、それでいいか」ってね。ただ、曲の長さには驚いた。みんな思いっきり伸ばしてたから。録音してるのは分かってたけど、Dizzy’sはいつもライブを録音してるから、とくに意識してなかったんだ。
レーベル側は「曲は長いけど、この夜の演奏をそのまま残すことに意味があるんだよ」って言ってね。「たしかに、それも悪くない話だよな。20年ぶりにまた集まれたんだし」って思ったよ。
—— 実際すごくいい作品です。演奏も素晴らしいですし。
ピーター : ありがとう。ただ、正直に言うと録音のサウンド自体はあんまり好きじゃない。ギターの音なんてひどいと思う(笑)。でも、Dizzy’sであのメンバーと演奏できたこと自体が最高だったし、あの3日間は本当に楽しかった。
たしか、ジェラルド・クレイトンとビル・スチュワートとやった別のセッションよりも前に録ったんだ。このときの曲のいくつかは、そっちでも演奏してる。だから『Signs of Life』再結成の録音が先で、ジェラルドのセッションのほうが後なんだよ。結局、そのセッションも『Let Loose』というタイトルでリリースすることになったんだけどね。
ソロ演奏への挑戦と発見
—— ソロ・ギター・アルバム『Live at Smalls』は、まったく別の作品というか、まるで違う生き物のようですね。
ピーター : 実は、これも録音するつもりじゃなかったんだ(笑)。
—— そうなんですか?このアルバムは、あなたのソロ演奏の魅力が本当によく出ています。僕も去年、ロックダウン前にソロ・ギターのコンサートをやったんですが、本当に怖くて。あなたはどうやってソロ演奏に向き合っているんですか?
ピーター : 僕も最初はとても怖かったよ。今でも怖い。そもそも録音する予定なんてなかったからね。ソロをやり始めたのは、Smallsで18時から19時半にソロ・ピアノをやってるのを見たのがきっかけなんだ。オーナーのスパイクに「なんでソロ・ギターはやらないの?」って聞いたら、「誰もやりたがらないからね。やりたいの?」って言うんだ。冗談半分で「まあ、やってもいいけど」って返したら「じゃあやってよ」って。そんな軽いノリから、本当にやることになっちゃったんだ。
実を言うと、僕がいちばん怖かったのは「ひとりでイントロを弾く」ことだった。誰かに「ギターでイントロつけて」って言われるだけで、もう心臓がバクバクして、「ひとりでどうすればいいんだ?」って(笑)。だから、これはもう正面から向き合うしかないと思ったんだ。「もし1セット、いや2セット弾ききれたら、もうイントロくらい怖くないだろう」ってね。
当時、アレンジした曲がいくつかあって、「Blood Count」はメロディだけソロ・アレンジを作っていたんだ。それで、いくつか小さなアレンジを出発点に演奏してみようと思った。というのも、僕は一度にたくさんのことを覚えておくのが苦手でね。曲の最初は覚えていても、2コーラス目に入ると「さて、次どうしよう?」ってなる。だから、短いアレンジを足がかりにして、そこから少しずつ広げていくようにしたんだ。
練習していくうちに、「ソロならもっといろいろできるじゃないか」と思うようになったんだ。他の楽器を気にせず、いろんな代理コードを試せるし、誰ともぶつからない。だから、自分で伴奏しながらソロを弾く感覚を模索していた。音がふわっと宙に浮いてしまわないように、どう支え、どう全体を満たすかを考えながらね。
僕にはフィンガースタイルの技術はないし、全部ピックで弾いているから、ジョー・パスのようなスタイルはできない。でも、自分にできる形でとにかくやってみようと思ったんだ。
ソロ演奏で学んだ“流れ”と“間”
—— モンクの曲も最高ですけど、「Giant Steps」も本当に素晴らしいですよね。
ピーター : 「Giant Steps」はよくドクター・ロニー・スミスと一緒にやってたんだ。彼はあの曲をまるで“溶かすように”すごく抽象的な形にしていくんだ。で、完全に自分の世界に入って、僕を置き去りにする。だから彼がそういう状態に入ったとき、自分はどうやって演奏を続ければいいんだ?って練習するようになった。
ピーター : それで気づいたんだ。時間の流れを自分で操れなきゃいけないって。ソロギターを学ぶことは、つまりルバートの使い方を学ぶことでもあった。ルバートからテンポのある演奏にどうやって戻るか、その流れをどうコントロールするか。自分が本気で信じて演奏すれば、聴いている人にもそれが伝わるんじゃないかと思ってね。
—— なるほど。
ピーター : だって、ドラムがいないからね(笑)。リズムを合わせる相手は自分しかいない。ルバートって本当に奥が深いんだ。テンポを止めてゆっくり弾くことじゃなくて、音楽の流れをコントロールすることなんだ。
偉大なシンガーや名伴奏者を聴くと、必ずしも一定のテンポで演奏しているわけじゃない。でもそれが本当に美しいんだ。音楽の流れに合わせて、ハーモニーがメロディを導いたり、メロディがハーモニーを導いたりする。まるでテニスのラリーみたいに、音が行き来するんだ。そのラリーを生むことが大事なんだ。
—— まさにそれがあなたの演奏から伝わってきます。単音を弾いているときでもスウィングしていて、ドラムが聴こえるようです。
ピーター : そう感じてもらえるならうれしいよ。いまもその感覚は練習中だけど、時間がある分、前より深く掘り下げているよ。
スモールズでの苦い経験と成長
—— 「ソロギター」って聞くだけで身構えてしまうんですが。
ピーター : わかるよ(笑)。僕もそう。毎回ソロで弾くたびに、必ず途中で「うわ、やらなきゃよかったな」って思う瞬間があるんだ。
—— 本当に?(笑)。
ピーター : 「ベースプレイヤーを呼べばよかった」とかね(笑)。最初にSmallsでソロをやり始めた頃は、1セット60分って決めていたんだけど、店の壁に掛かってる時計が目に入るんだ。数曲弾いたあと、「もう限界かも」と思って時計を見ると、まだ6分しか経ってない。「うそだろ…あと54分もあるのか!? どうすりゃいいんだ!?」って(笑)。
でも不思議と、いつも2セット目のほうがうまくいくんだ。落ち着いて、「もうどうにでもなれ」って吹っ切れるんだよ。そうすると自然といい演奏ができる。4小節くらい、「今のはよかった」って思う瞬間があって、「4小節できるなら、1曲まるごとできるはずだろ?1曲いい演奏ができるなら、1セット全部だっていい演奏ができるはずだろ?」って少しずつ考え方が変わっていった。
結局のところ、すべては集中力なんだ。その瞬間に自分が何をすべきかに集中して、ひとりでステージに立っていることを怖がらずに、音楽のために演奏する。それが一番大切なんだよ。
—— なるほど。
巨匠たちとの出会い
—— リー・コニッツのアルバム『Parallels』について教えてください。
ピーター : 彼とは、僕が高校生のときに出会ったんだ。僕が育ったアパートに彼が住んでてね。たしか中学から高校に上がる頃だったかな。ある日、同じアパートの知り合いの女性が「あなたジャズが好きなのね?じゃあリー・コニッツを知ってる?8階に住んでるのよ」って。僕は「もちろん知ってます!本で読んだことあります!」って答えたけど、まさか同じアパートに住んでいるなんて思ってもみなかった。
それで、ある日エレベーターで偶然会ったんだ。僕は12階に住んでいたんだけど、その日はリンカーン・センターの図書館から何枚かレコードを借りてきた帰りでね。その中の1枚が、リー・コニッツのアルバムだった。8階でエレベーターが止まって乗ってきたのが彼だった。すると僕の持っていたレコードを見て「おい、それ、俺のレコードだ」って言ったんだ(笑)。
それが最初の出会いだった。僕は慌てて「こんにちは、ミスター・コニッツ。僕、ピーターです。この建物に住んでて、知り合いの女性からあなたのことを聞いて、いつかお会いしたいと思ってました!」って言ったよ。ものすごく緊張しながらね。
それから、彼がアッティラ・ゾラーの友人だと知ったんだ。僕は別のきっかけでゾラーに習うようになったんだけど、その縁もあってリーとも自然に仲良くなった。彼は僕にとって、人生で初めて間近で出会った有名なジャズミュージシャンだったんだ。だから特別な存在なんだよ。
—— そうだったんですね。
ピーター : 彼はいつも優しくて、演奏のたびに僕をステージに上げてくれた。レッスンを一度受けたあと、「今度は一緒に何曲かやろうよ」って誘ってくれたんだ。音で会話をするのが好きな人で、誰かがコンピングしてくれるのを楽しんでたんだと思う。テーマをユニゾンで弾いたりもしたし、とても気さくで、ジャムが大好きな人だったよ。
90年代の初めごろは、いくつかのギグに呼んでもらってね。そのあと、チェスキー・レコードの録音の話がきたんだ。
—— それが「Parallels」ですね。
ピーター : そう。ちょっと変わったセッションで、1本のマイクを中央に立てて、全員がその周りを囲んで録るんだ。まるでオーディオマニアの実験みたいで(笑)。でもすごく楽しかった。録音場所が教会で、独特な響きのする空間だったけど、それがまたよかったね。マーク・ターナーも一緒で、本当にいい経験だった。
その後もリーとは何度も会っているけど、いつもあの独特の温かい雰囲気があったよ。
ルー・ドナルドソンとリー・コニッツ
ピーター : 22、23歳の頃、ルー・ドナルドソンのバンドで弾き始めたんだけど、ルーとリーって同じ世代なのにまるで正反対の存在なんだ。ふたりともチャーリー・パーカー以降の世代だけど、音楽の方向性がまったく違ってね。リーはよく僕に、「お前、ルー・ドナルドソンとやってるのか。ああいう感じの音楽をやるのか」なんて、少しからかうように言ってきたりして(笑)。
ピーター : 僕はオルガン・カルテットで演奏することも多かったから、リーが好むリニアで実験的な方向とは少し違ってたんだ。だからリーとやるときは、彼が求めてたようなもっと遠くへ行く感じにはまだ届いてなかったと思う。でも、リーやマーク・ターナーのためにコンピングするのは本当に楽しかった。ただ、あの頃はまだ、コンピングを掴みきれていなかった時期でもあったんだ。
—— いやいや(笑)。
ピーター : ほんとに(笑)。今はだいぶマシになったけどね。でも楽しかったし、あの人たちと一緒に演奏できたのは幸せだった。
それから4〜5年前にリーから電話があってね。「昔のCDをいろいろ聴き返してたら、お前とマークとやったやつを見つけたんだ。あれ、すごく良かったよ」って。「発売当時は聴いてなかったけど、今聴いたらいいね」って言ってくれて。僕も自分の作品は出したあとあまり聴かないから、その気持ちよくわかる(笑)。
でも、そんなふうに言ってもらえて本当に嬉しかったよ。「当時は気づかなかったけど、お前いい演奏してたな」って言われて、心から幸せだった。
—— いい話ですね。
ピーター : うん。リーは本当に唯一無二の存在だったよ。音楽も、人柄もね。
ウェスからグラント・グリーンへ
—— あなたはこれまで、本当に多くの偉大なミュージシャンと共演してきましたよね。
ピーター : そうだね。本当に運が良かったと思うよ。
—— 例えば、ウェスと共演したオルガン奏者のメルヴィン・ラインとか。
ピーター : うん。僕はずっと、憧れの人たちと直接じゃないけど、一歩手前の距離で繋がってきたんだ。メルヴィンからはウェスの話をたくさん聞いたし、ルー・ドナルドソンからはグラント・グリーンの話をたくさん聞いた。そうやって、ヒーローたちと間接的に繋がれたのは本当に幸運だった。
—— 素晴らしいですね。
ピーター : メルヴィンもドクター・ロニー・スミスも、本当に多くのことを教えてくれた。ルーやロニーと一緒に演奏できたのは最高の経験だったし、ロニーとトリオでもレコーディングできたんだ。
ピーター : ルーのバンドでロニーが弾くときは、彼は完全にルーの音楽の中で自分の個性を活かしていた。ルー自身がすごく強いキャラクターだったから、僕ら全員が彼を支える形だったんだ。でもロニーがリーダーのときは、音楽がまったく違う方向へ広がっていった。
—— もっと自由な感じだったんですね。
ピーター : うん。ロニーはいろいろクレイジーなこと試してたよ。あれは本当に貴重な経験だった。ちょうど僕も、彼とどう向き合って演奏すればいいのか少しずつ掴めてきた頃だったんだ。
その頃のロニーはもっとファンク寄りに進もうとしていてね。ある日、家に呼ばれて「おい、ペダル持ってるか?」って言うんだ。ちょっと変わった音とか、もっとディープなファンクのサウンドを出したかったみたいなんだ。
僕が持っていたのは緑色のペダルとワウくらい。それを使って一緒に試してみたんだけど、「きっとロニーはもっとファンク寄りで、ペダルを自在に使えるギタリストを探してるんだろうな」と感じた。僕はまだ、自分の音を模索してる途中だったし、ペダルを繋ぐと音の反応やフレージングが変わってしまう気がしてたんだ。
だから、ペダルを前提にした演奏には馴染めなかった。いつか自分の中でそういうサウンドをちゃんと活かせるようになったら、また挑戦しようってね。
ペダルを使わない理由──“楽器そのもの”への敬意
ピーター : 今もペダルは使っていないけど、「使うな」なんて言うつもりは全然ないよ。ギターとアンプっていうのは、まだまだ発展の余地があるし、進化を止めるべきじゃない。ただ、「ペダルを使わないギタリスト」が特別な目で見られるのは、ちょっと不思議だなと思うんだ。
だって、ピアニストに向かって「ピアノ上手いね。でもなんでシンセサイザー使わないの?」なんて言わないでしょ?ピアノトリオで演奏していても「ローズはどこ?」「シンセは?」なんて言われない。ピアノという楽器そのものが、ひとつの完成された存在として尊敬されているからだと思う。
でもギターは違うんだ。「ペダル使わないの?」「ギターだけ?」って言われる。まるで、僕が中世の音楽でも弾いてるみたいに思われるんだよ。でも僕は、この楽器そのもので音楽を作りたいだけなんだ。ペダルを使うかどうかじゃなくて、何を弾くか。演奏の内容こそが、音楽を古くも新しくもする。ギターって、どうしても機材文化と切っても切り離せない楽器だから、そこが面白くもあり、難しいところだね。
―― たしかに。
ピーター : ペダルって、「足でも音を操れるようにしよう」っていう発想から生まれたものなんだ。つまり、音をコントロールする手段がひとつ増えただけ。そういう意味では、ピアニストって本当にすごいと思うよ。彼らはその場にあるピアノで勝負するしかないし、もし調律が悪くても、スイッチひとつで音を変えることなんてできない。すべてを受け入れて弾くしかないんだ。
その点、ギタリストにはアンプがある。ベースやトレブル、リバーブをいじって、理想の音に近づけることができる。でもピアニストはそれができない。だからこそ、音そのものから出る力っていうのをすごく尊敬してるんだ。
とはいえ、ちょっと不公平に感じることもあるよね。アコースティックピアノを弾けば「かっこいい」って言われるのに、ギターをペダルなしで弾くと「なんでペダル使わないの?」って聞かれる。僕はいつも「いや、これが自分にとって自然な形なんだ」って答えてるよ。
Samo SalamonのYouTubeチャンネル
今回のインタビュー動画を公開しているのは、スロベニア出身のギタリスト、Samo Salamon(サモ・サラモン)さんのYouTubeチャンネルです。
ジャズギタリストへの深いリスペクトと鋭い洞察にあふれた内容で、見ごたえのあるインタビューばかり。
ぜひチャンネルでチェックしてみてください。


![ホワッツ・カムズ・ネクスト / ピーター・バーンスタイン (What Comes Next / Peter Bernstein) [CD] [Import] [日本語帯・解説付] [Live]](https://m.media-amazon.com/images/I/51YBw2yo4cL._SL160_.jpg)
![橋 (完全生産限定盤) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51g4MZRdSDL._SL160_.jpg)