現代ジャズ・フュージョンの巨匠、スコット・ヘンダーソン。
新作『Karnevel!』のリリースを機に行われたロングインタビューでは、作曲の試行錯誤から即興への向き合い方、そして止まることのない創造への情熱までが語られた。
“進化し続ける”ギタリストが見つめる、音楽の本質とは——。
*本記事は、Samo Šalamon氏の許可を得て日本語に翻訳・編集したものです。
『Karnevel!』が生まれるまで
—— まずは新しいアルバムを送っていただいてありがとうございます。先週ずっと聴いていました。うちの娘(11か月)もノリノリで、踊りまくってました(笑)。本当に素晴らしいアルバムですね。
スコット : ありがとう。
—— 「Puerto Madero」や「Haunted Ballroom」など、美しい曲が多いですよね。それに「Covid Vaccination」にはユーモアな雰囲気もあってすごく気に入っています。普段はどのように曲を作っているんですか?
スコット : それは難しい質問だね。というのも、曲がどうやってできたのか、あまり覚えていないんだ。僕は作業が早いほうじゃなくて、曲を形にするまで何週間もかけて、少しずつ進めていくタイプだからね。出来上がる頃には、どの瞬間に何を思って書いたのかはほとんど覚えていないんだ。
いつも試行錯誤を重ねて、しっくりこないアイデアを見直しながら、ようやく「これだ」と思えるものにたどり着く。
でも、コロナ禍のあいだは少し違っていた。ツアーができなかった分、ソロギターをじっくり練習する時間が取れたんだ。もともとソロギターを得意とするタイプではないし、ソロでツアーをしようとも思っていなかった。でも、自分の頭の中にあるハーモニーを瞬時にギターで表現できる力が必要だと感じてね。
それまでは「このコードはどうだろう?」「いや違うな、じゃあ次はこれ」っていうように、時間をかけて探っていた。でも、1年ほどソロギターを練習するうちに、頭の中で鳴っている音をそのまま弾けるようになってきたんだ。
そのおかげで、今回の曲は、以前よりもずっとリアルタイムで生まれた。録音しながら弾いたフレーズの中で、気に入ったものを曲の核にしていく。そういう流れが、これまでよりずっと自然になったんだ。
もちろん、まだキース・ジャレットのような境地には遠いけど(笑)、少しずつ進歩していると思うよ。
才能よりも努力
—— あなたの音楽を聴くたびに、いつも作曲のセンスに驚かされます。トライバル・テックの「Stella in Infrared」なんて、今でも授業で取り上げているんですよ。
スコット : ありがとう。僕にとって作曲というのは、才能よりも努力がすべてなんだ。特別才能があるとは思っていないし、むしろ「気に入るものができるまで徹底的にやる」タイプだよ。
たいていの人は、最初の段階で良いアイデアが出ないと「自分には無理だ」と諦めてしまう。でも、そうじゃない。本当に良いものを作るには、粘り強く続けるしかない。
作曲って、僕にとっては彫刻をするような作業なんだ。ちょっと失敗したからって、彫刻全体を壊して新しい石を用意する人はいないだろ?少しずつ削って、形を整えて、気に入らない部分を直していく。その積み重ねで作品は完成していく。
僕の曲作りもそれと同じで、1日ごとに「少し手を加える」ことの繰り返しなんだ。気に入った部分は残し、気になる部分は直す。そうやって数週間、時には何か月もかけて磨き上げていく。本気でその過程を続けられるなら、誰だって良い曲を書けると思うよ。
でも、みんなすぐに結果を求めたがるんだ。僕が身をもって学んだことは、自分に対して辛抱強くあることなんだ。時間がかかっても、やり続ければ必ず良い結果が出る。その日は来ないように思えても、信じて続ければ、いつか必ず形になる。
—— あなたの口からその言葉を聞けるのは本当に励みになります。
スコット : 僕の生徒たちを見ていても、まさにそう思うんだ。生徒が自作の曲を持ってきてくれて、「ここはいいけど、この部分をもう少しこうしてみたら?」とアドバイスをする。そして数週間後にまた持ってくると、見違えるように良くなっていることがある。そこにはちゃんと努力の跡があるんだ。
そういうのを見ると、「努力すれば誰にだってできるんだ」と感じるよ。大事なのは、簡単に諦めないことなんだ。
ルーツと影響 ― ロックからジャズへ
—— 作曲を始めたのはいつ頃だったんですか?
スコット : 15歳の頃にはもう作曲をしていたね。
僕が一番大きな影響を受けたのは、レッド・ツェッペリンなんだ。今でもお気に入りのロックバンドだよ。彼らに惹かれたのは演奏の素晴らしさだけじゃなくて、曲そのものの構成力とセンス。あの時代にして、信じられないほど進んでいた。
—— 同感です。昨日ちょうどレッスンで「The Ocean」を教えていたところでした。
スコット : 本当に素晴らしい音楽だよね。ジミー・ペイジは僕にとって、作曲家としても、スタジオ・ミュージシャンとしても大きな存在なんだ。それに彼は、音を重ねて奥行きのあるサウンドを作り出すという発想を持っていた。複数のギターパートを重ねて立体的なサウンドを構築する──それをいち早く始めたのが彼だったと思う。
レス・ポールも多重録音の先駆者ではあるけれど、少なくとも当時のロックバンドで、ギターの立体的なサウンドを実践したのがジミーだった。
そしてもう一人、リッチー・ブラックモアもそうだった。あまり気づかれないけど、彼もかなりギターを重ねていたんだ。
—— そうなんですね。
スコット : あるウェブサイトでリッチーのギター・トラックだけを聴いたんだけど、どの曲にも5〜6本のギターが入っていたんだ。
彼は、ベースとユニゾンするとき、左チャンネルには中域を強調したギターを、右チャンネルには低音と高音をブーストしたギターを重ねて録っていた。それをステレオで合わせると、ものすごく立体的で厚みのある音になる。
ほとんどの人はギター1本の音だと思って聴いているけど、実はそうじゃない。ただディープ・パープルの場合はキーボードも入っているから、ツェッペリンのようにそのレイヤーがはっきり聴こえるわけじゃないんだ。でも実際には、ほとんどすべてのディープ・パープルの曲でリッチーは重ね録りをしていたんだよ。
—— ジェフ・ベックも多重録音をしていましたよね。
スコット : そうだね。「Blow by Blow」や「Wired」はギターが幾重にも重なってる。
黒人音楽との出会い
—— ギタリストの演奏をコピーして学んでいたんですか?
スコット : そこまで徹底してはやらなかったけど、影響はすごく受けたよ。ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモア、ジミー・ペイジ、そしてカルロス・サンタナ──あの時代のギタリストたちは僕にとって大きな存在だった。
サンタナの『Abraxas』や『Caravanserai』はよく聴いていたし、「Song of the Wind」のギターソロなんて本当に素晴らしい。
—— そこからどうやってジャズに入っていったんですか?
スコット : きっかけは、黒人のバンドに雇われたことなんだ。そのグループには4〜5年在籍していて、僕だけが白人だった。
でも当時の僕は、黒人音楽のことをまったく知らなかった。子どものころから白人ロックばかり聴いて育ったからね。BB・キングやアルバート・キング、アルバート・コリンズ、マディ・ウォーターズ……イギリスのロックバンドたちが影響を受けたアーティストたちの存在さえ知らなかった。
後になってから、「ああ、レッド・ツェッペリンはマディ・ウォーターズなしには存在しなかったんだ」と気づいた。要するに、ブルースという黒人音楽がロックのルーツだったんだよね。
そのバンドでは、モータウンの曲やジェームス・ブラウン、クール・アンド・ザ・ギャング、タワー・オブ・パワーなど、あらゆるファンクやR&Bの名曲を演奏していた。僕らはクラブのハウスバンドで、ツアー中の有名なR&Bシンガーたちのバックも務めていたんだ。
そうした経験から、R&Bやファンクもロックと同じくらい好きになった。そしてR&Bやファンクの中には、ロックよりもジャズの要素が色濃く含まれていることに気づいたんだ。特にタワー・オブ・パワーは、サックス奏者がジャズの語彙でソロを吹いていて、それが僕をフュージョンの世界へと導いた。
そこからウェザー・リポートなどを聴くようになって、ロックとファンクとジャズが混ざり合う実験的な音楽に惹かれていった。当時はまだフュージョンという言葉も新しくてね。ストレート・アヘッド・ジャズよりも聴きやすかったんだ。
でも次第に、ブルースを学んだときと同じように、ジャズもルーツから学ぶ必要があると感じるようになった。ウェザー・リポートの音楽を本当に理解するためには、チャーリー・パーカーやジョン・コルトレーンを聴く必要があったんだ。彼らが1940年代に築いた語彙を基盤に、現代のミュージシャンが音楽を作っていたからね。
そうしてストレート・アヘッド・ジャズを聴くようになって、いろんなジャンルの影響が自分の中で混ざり合っていった。いまの僕は、特定のジャンルに“好き・嫌い”はない。ただ“良い音楽”が好きなんだ。
どんなスタイルであっても、良いものなら好きになる。音楽に優劣はないし、どんなジャンルにも素晴らしいものはあると思っている。
混ざり合いから生まれる個性
—— 興味深いのは、今挙げたような影響が、すでに初期の作品にも表れていることです。デビュー当時から「これはスコット・ヘンダーソンだ」とすぐ分かるサウンドを持っていた。つまり、かなり早い段階で自分のスタイルを確立していた、ということですよね。
スコット : そうかもしれないね。結局のところ、どれだけ多くの影響を自分の中に取り込むかが大事なんだと思う。誰だって他のミュージシャンから影響を受けている。「彼は唯一無二の存在だ」と言われる人だって、必ず何かの影響を受けているものなんだ。
たとえばスティーヴィー・レイ・ヴォーン。彼は自分のスタイルを築いた革新的なギタリストだけど、
そのプレイには明らかにアルバート・キングやジミ・ヘンドリックスの影響がある。それは「模倣」じゃなくて、吸収して新しい形にしているということ。
マイケル・ブレッカーだってコルトレーンから強い影響を受けていたけど、そこに多くの別の要素を加えて、彼自身の声を作り上げた。同じように、レニー・ブローがフィリップ・デグリーや多くのジャズギタリストに影響を与えたし、チェット・アトキンスもいろんなプレイヤーの中に息づいている。結局、音楽は影響の連鎖の中で進化していくんだよ。
ザヴィヌルが教えてくれた“本当の即興”
—— 先ほどウェザー・リポートの話が出ましたが、ジョー・ザヴィヌルとの共演が始まった頃のことを覚えていますか?
スコット : もちろん。あのときのプレッシャーは今でも覚えてるよ。だってジョーは、それまで毎晩ウェイン・ショーターの演奏を聴いていたんだ。そんな人が、僕の音を聴くんだよ?そりゃあ緊張するに決まってる。
最初は気負っていたけど、できる限りのことをやった。僕はもともとリックを弾くタイプのギタリストだったけど、ジョーの音楽ではそれを完全に捨てる必要があった。彼はリックが大嫌いだったんだ。
少しでもビ・バップっぽいフレーズを弾くと、すぐに気づかれる。そして遠慮なく言ってきたよ。「そんなビ・バップのフレーズ、俺のバンドでは弾くな。これはビ・バップ・バンドじゃない。誰かのコピーを弾くんじゃなくて、自分で即興しろ」ってね。
それを言われたときは本当にショックだった。当時の僕にとってリックこそがギターの全てだったからね。自分で音を生み出すというより、他のミュージシャンのフレーズを引用して弾いていたんだ。
今なら分かるけど、当時の僕はまだ即興を理解していなかった。もし今もう一度ジョーと演奏できるなら、あの頃よりずっと“自分の言葉”で弾けると思う。今なら、彼が求めていたものをもっと表現できるはずだよ。
コピーではなく、自分の音で弾け
スコット : 今でもよく覚えているのが、「Little Rootie Tootie」というモンクの曲を録音したときのこと。ジョーが「この曲でソロを弾いてみろ」と言ってくれて、数時間もらって録音に臨んだんだ。
リズムチェンジのコード進行も追えて、自分ではかなり良いソロを録れたと思った。でもジョーがスタジオに入ってきて言ったんだ。「それ、全部消せ。チャーリー・クリスチャンの演奏が欲しかったら、本人を掘り起こして弾かせてるよ」って。
あれはさすがに堪えたよ。でもそのあとジョーが言ったんだ。「もう一度録ってみろ。今度は“自分の音”で弾け」って。
それで一発録りしたテイクが、そのままアルバムに収録されたんだ。ビ・バップにならないように意識して、ブルースよりな演奏をした。ジョーが求めていたのは、そういうよりモダンなアプローチだったんだ。50年代のビ・バップ奏者のコピーなんてまったく望んでいなかった。
スコット : ジョーはキャノンボール・アダレイのバンドで長くビ・バップを演奏したから、もうあのスタイルは飽きていたんだと思う。
そこから彼は、まったく新しい道を選んだんだ。ウェイン・ショーターと新しいバンドを始めて、それまでのビ・バップとはまったく違う方向へ進むことを決めた。よりメロディックで創造的な、新しい音楽の形を追求する——それは勇気のいる決断だったと思う。
当時、ジャズ批評家たちは彼らの音楽をまったく受け入れなかった。でもそれは、コルトレーンが『A Love Supreme』を出したときや、マイルス・デイヴィスが『Bitches Brew』を発表したときと同じことなんだ。
「どうして“Stella by Starlight”をやらないんだ?」「“All of Me”をやってくれよ」そう言う人がいっぱいいた。
けれど、真のアーティストはリスクを取る。そのときは理解されなくても、後になって評価される。ジョーもまさにそうだったんだ。
厳しくて、でも最高に面白い人だった
—— ツアー中のジョーはどんな感じの人でしたか?
スコット : ジョーはね……とても怖かったよ(笑)。でもその“怖さ”がまた最高でね。とにかくすごく意地悪なんだけど、同時に最高に面白い人だったんだ。何を言われても腹が立たない。全部ジョークみたいなんだよ。
きっとコメディアンでも成功できたと思う(笑)。どんなに辛辣なことを言っても、いつも笑わせてくれる。だから「厳しいけど憎めない」——そんな人だった。それに、彼も他の多くのバンドリーダーと同じで、自分の求めるサウンドを非常に明確に持っていた。
僕のバンドでは、メンバーに細かく「こうしてくれ」と言う必要がないんだ。みんな自然と何をすべきか分かっているからね。
でもジョーのバンドでは、そうじゃないメンバーもいた。ときには“弾きすぎる”人もいて、全体のバランスが崩れることもあった。正直言って、当時の自分のトーンもまだまだだったと思う。ただ、バンドを離れて5年ほど経った頃に、ジョーがこう言ってくれたんだ。
「お前は、俺が一緒に演奏した中で最高のアンサンブル・プレイヤーだ。」
—— うわあ……それはすごい言葉ですね。
スコット : 彼がなぜそう言ったのか、僕にはよく分かるんだ。当時の僕は即興なんて全然できてなかったから「最高の即興演奏者だった」なんて言えるわけがない(笑)。でもバンド全体の構成を支える役割には向いていたんだ。
ライブの中で、曲の構成を整理したり、サウンドの方向性を提案したり、ステージ上でアレンジを導いたり——そういう役割を自然にやっていた。それはちょうど、ジャコ・パストリアスがウェザー・リポートでやっていたことに近かった。
ウェインの曲はウェイン自身が構成していたけど、ジョーはもともとジャムが大好きで、放っておくとどの曲も20分くらいになっちゃう。だからジャコが「そろそろ次に行こう」「ここで切り替えよう」「このセクションは半分にしよう」と、常に音楽を“観客の視点”から調整していた。
僕はジョーのバンドでその役割を担ったんだ。ステージ上で、曲をどこで展開させるかの“合図”を出す。ジョーもそれを理解していて、「演奏を切り替えるタイミングだと思ったら、合図を出してくれ。俺がムッとしても気にするな。俺はジャムが好きだから切られるのは嫌だけど、それでもやってくれ。1ステージで2曲しかできなくなるからな」(笑)って言っていた。
つまり、ジョー自身も自覚していたんだよね。自分が放っておくと“暴走”するタイプだって。だから、「アンサンブル・プレイヤーとして最高だ」という言葉は、僕にとって本当に嬉しい褒め言葉だった。
—— チック・コリアはその正反対のタイプですよね?
スコット : そうだね。チックはすべてが事前に構築された音楽だった。アレンジも構成もすべてが緻密に決められていて、僕の助けなんて必要なかった。完璧主義者だったね。
—— 音楽的にも、ジョーの方がオープンですよね。
スコット : そうだね。僕自身のバンドでは、その二人の中間を目指しているんだ。作曲されたセクションは持ちつつも、夜ごとに演奏が変化できる自由を残しておきたい。
良いコンサートって、作曲部分と即興部分が上手く混ざっていると思うんだ。もし毎晩同じように演奏していたら、ただの“ヒット曲カバー・バンド”みたいになってしまう。それでは演奏者にとっても聴き手にとっても退屈だ。だから演奏って、まるでサーカスの綱渡りみたいなものなんだ。毎晩少しずつ違うことをやりながら、落ちないようにバランスを取る。
最悪なのは、「あ、これ昨日と全く同じだな……」と演奏中に気づく瞬間だよ。そう感じたら、セクションを削ったり、構造を変えたりして、メンバー同士の“会話”が生まれるようにする。音楽は常に会話的でなければならない。そのバランスを保つのは難しいけど、僕たちはいつもそこを目指しているんだ。
即興と創造―“恐れずに音を出す”ために
—— 去年、17日間で17本ライブをするツアーをやったんですが、10本目くらいで“壁”にぶつかりました。演奏は良いし、観客も喜んでくれている。でも自分の中で「また同じことをやってる」「同じソロを繰り返してる」と感じて、ちょっとしたスランプになってしまって。
スコット : 分かるよ。僕もまったく同じ問題を抱えてる。
—— 毎晩フレッシュでいるためにはどうすればいいですか?
スコット : 正直に言えば、完璧な解決法はないね。次の日に突然「別の自分」になれるわけないからね。指をパチンと鳴らして、まったく違う人間になれれば苦労しないけど(笑)。
自分が持っているもので演奏している以上、ある程度の繰り返しは避けられない。だからこそ、何か新しいことを試す時間を作るようにしている。たとえば「今夜この曲で別のアプローチをしてみよう」とか、「バンドを驚かせるようなアイデアを仕込んでみよう」と考えるんだ。
コード・ボイシングを変えてみる、リズムをずらしてみる、音量やトーンを変えてみる——そういう小さな変化で十分。特にトリオ編成では、ボイシングを極端に変えることはできないけど、リズム面ではかなりの自由がある。同じコードでも違うリズムで弾いたり、強弱を変えたりするだけで演奏の表情はまったく変わるんだ。
もし日中に少し時間が取れたら、「このセクションは別のハーモニーを試してみよう」とか、「このコードを別のボイシングに置き換えてみよう」と考えてみる。そうやって他のメンバーの耳を引きつける工夫をすると、バンド全体のエネルギーが新しくなるんだ。
もちろん、ツアー中は時間がなくて毎回それができるわけじゃない。そんなときは、「自分の書いたものには責任を持つ」と割り切って、同じように弾くしかない。それもステージの一部として受け入れるんだ。
自分の音より全体の音を聴くということ
スコット : でもね、そういう構成が決まっているセクションと対照的に、どんなことも起こり得るオープンなセクションを作っておくといい。そうすれば、「自分ひとりで変化を作らなきゃ」と思わなくていい。バンド全体で何かを起こせるからね。
つまり、自分にばかり意識を向けず、「周りの音を聴く」ことが大事なんだ。ビル・フリゼールが『Guitar Player』誌のインタビューで言ってたんだけど、「ギターを弾くうえでの第一のルールは“聴くこと”だ」って。
本当にその通りだと思う。多くのギタリストは、自分の音しか聴いていない。でも実際には、周りを聴くほど演奏は楽になるし、楽しくもなる。
自己意識が強すぎると、たいてい演奏は硬くなる。逆に周りを聴いて、音の“会話”に耳を傾けると、自然とアイデアが湧いて、スペースも生まれ創造的になれる。
だから僕はビルに心から敬意を払ってる。彼は本当に経験豊かで、クリエイティブなギタリストだと思う。あのインタビューも素晴らしかったよ。「ギタリストが演奏を良くするための10のポイント」という特集だった。
—— ビルのライブは何度か観ましたが、本当に“チームプレイヤー”ですよね。12曲演奏しても、ソロを取るのはせいぜい2回くらい。まるでシカゴ・ブルズのスコッティ・ピッペンみたいに、チーム全体を支えるタイプ。
スコット : まさにそうだね。ビルの素晴らしさは、チームプレイヤーでありながら、常に創造的なところ。決して“見せびらかす”タイプじゃない。彼にとって重要なのは、周囲と関係しながら音を作ることなんだ。
だから彼の演奏はいつも、バンドの流れや空気にぴったり合っている。「今ここで何が起きているか」に反応して生まれる音だから、毎回違っていて、本当に生きている。
一方で、多くのギタリストは自分の“リック”を弾くだけで、バンドが何をしていても関係なく同じことを繰り返す。でもビルは違う。「今そこにある音」を聴いて、そこから生まれる。だからこそ、あんなにクリエイティブなんだよ。
トライバル・テックから『Dog Party』へ
—— チームプレイヤーといえば、トライバル・テックは本当に素晴らしかったですよね。
スコット : うん、まあ……良い夜もあったけど、悪い夜もあったね。トライバル・テックで唯一悔やんでいるのは――とにかく音がデカすぎたこと。
—— 3回ライブを観ましたけど……確かに大きかったです(笑)。
スコット : 本来ならいい演奏になっていたはずの瞬間が、音量のせいで台無しになったことが何度もあったんだ。本当にクリエイティブなことって、実は小さい音量でやってるときに起こるんだよ。お互いの音がよく聴こえて、会話できているときにね。
でも音が大きすぎると、部屋全体が共鳴して全部がただのノイズの塊みたいに聞こえるんだ。各メンバーが何をしているのか分からなくなって、音楽的な対話のチャンスを失う。あれがトライバル・テックの最大の失敗だったと思う。
正直に言うと、その原因はカーク・コヴィントンとゲイリー・ウィリスにあった。この二人は、今でも僕が一緒にやった中で最も音のデカいリズム隊だよ。
—— カークは本当に音がデカいですよね。
スコット : 信じられないくらいだよ(笑)。優れたプレイヤーなんだけど、会場に合わせて演奏するという感覚がなかった。どこで演奏しても全力。特にカークなんて、50人のクラブでも野外フェスでも同じ勢いでドラムを叩くんだ。残念だけど、それでバンドとしての可能性が少し損なわれた気がする。
—— アルバムではバランスがすごく良いですよね。
スコット : レコーディングではコントロールできるからね。スタジオではちゃんとお互いを聴ける状態を作れる。だから演奏もずっと音楽的だった。正直、ライブよりもレコーディングのほうがはるかに出来が良かったと思うよ。
—— ツアーはどうでしたか?
スコット : トライバル・テックのツアーはね、今のトリオより音楽的ではなかったと思う。今のバンドは、トライバル・テックの半分くらいの音量で演奏してる。
—— 半分ですか?
スコット : うん。音量はあるけど、常識的な範囲だね。僕らはダイナミクスを大事にしてる。大きい音もあれば、小さい音もある。強さの中に緩急があるから、演奏が呼吸するんだ。トライバル・テックは常にフルボリュームで、ダイナミクスがなかった。それが唯一の反省点だと思う。
大音量で失われる“コントロール”
—— 90年代初期の『Face First』や『Reality Check』では、フュージョンを新しい形でよみがえらせたように感じました。
スコット : 曲のクオリティもメンバーの実力もすごく良かったんだけどね。ただ、ライブでは音圧がすべてを壊していた。僕は、大音量の中ではうまく弾けないタイプなんだ。
音があるレベルを超えると、ギターのコントロールを失う感覚になる。変なフィードバックが出て、しかも“いいフィードバック”じゃない(笑)。レガートを弾こうとしても、全ての音が暴れ出してしまう。
音量が大きすぎると、トーンをコントロールできなくなるんだ。僕には、自分が一番良い音を出せる音量のゾーンがある。力強くて存在感のあるサウンドだけど、耳が痛くなるほどではない。そのバランスの中でこそ、本当に気持ちよく弾ける。
—— なるほど。
スコット : ありがたいことに、僕のアンプにはマスターボリュームがあるからね。だから、小さなクラブでマーシャルを“10”にして鳴らさなくても、十分に歪んだ理想のトーンが作れるんだ。これには本当に助けられてるよ。
“実験”から“演奏”へ
—— 「Dog Party」を作った時期はトライバル・テックの活動と重なっていましたよね。あのアルバムを作ろうと思ったきっかけは何だったんですか?
スコット : 当時のトライバル・テックは、スタジオでとてもテクニカルな作業をしていたんだ。まだデジタル録音やPro Toolsが登場する前で、僕らは24トラックのテープに60トラック分のキーボードを詰め込もうとしていた。とにかくキーボード主体のバンドだったから、SMPTEトラックを使って同期させて、ミックス時にも鍵盤の音を鳴らしながら処理していた。
そうやってどんどん作業が複雑になっていって、「これはもう音楽じゃなくて、機械と格闘しているだけだな」って感じるようになったんだ。それで、昔みたいにバンドで集まって、録音ボタンを押して演奏するだけのアルバムを作りたくなった。それが『Dog Party』を作るきっかけだよ。
—— 『Dog Party』は構成がすごく緻密ですよね。そんなに音を重ねていないのに、サウンドの厚みを感じます。
スコット : 実はけっこう重ねてるんだけど、できるだけ自然な一体感を持たせたんだ。難しいのは、“ギタリストとしての自分”と“プロデューサーとしての自分”のバランスを取ること。
即興を愛するギタリストの一方で、オリジナル作品を作る作曲家であり、プロデューサーでもある。僕はスタンダードを弾かないし、スタンダードをリハーモナイズして演奏するタイプのジャズ・ギタリストでもない。自分の音楽を作りたいんだ。
よくあるように、ライブを録音しただけのアルバムではなく、もっと特別なものにしたいと思っている。「たまたまマイクがあって録音された一夜」ではなくてね。
もちろんライブ盤も出しているし、また作ると思う。でも、それは本当に“ありのまま”。音を重ねたりせず、ステージでのサウンドを残しただけなんだ。それに、僕はそう頻繁にアルバムを作るわけじゃない。だからこそ、一枚一枚を特別な作品にしたいと思っているんだ。
ライブの“瞬間”とスタジオの“構築”
スコット : ライブではギターでコードとメロディを同時に弾いて、ベースとドラムを加えたトリオ編成で曲をふくらませる。それだけで十分成立するんだ。でもレコーディングでは、トップノートをギターで重ねたり、ボイシングを追加して、まるでピアノのように音を広げたりする。
もちろん、そういう重ね方はライブでは再現できない。でも気にしてないよ。限られた音数でもしっかり表現できるし、聴いている人にもどの曲かちゃんと伝わるからね。レコードほど厚みのあるサウンドにはならないけど──まあトリオだし、そのへんは勘弁してくれよ(笑)。
それでも、スタジオではそうした“追加のボイシング”を入れるのが好きなんだ。その方が全体がより豊かで、より調和的に聴こえるし、何よりいろんなサウンドを試すのが本当に楽しい。何百というペダルを試したり、違うトーンを探ったりしてね。
スティーリー・ダンやウェザー・リポートがやっていたように、ホーンセクションやバック・ボーカルを加えたり、ギターパートを3本も4本も重ねたりして、作品全体を大きな映画のようなスケールにしていく。もう演劇じゃなくて、映画なんだよ(笑)。
作るという過程が好きだし、プロデュースも同じくらい楽しんでいる。だからその時点では、ギタリストというよりプロデューサーなんだ。今はちょっと腕がなまってる。アルバムを完成させたばかりで、ミックスやレイヤー作業、マスタリングに追われて、普段のようにギターを弾く時間が取れなかったんだ。
でも今はやっと一段落ついたから、また練習に戻れる。これから数か月は毎日8時間くらい練習して、以前の調子を取り戻すつもりだよ。
「練習」と「即興」は両立しない?
—— どんな練習をしているんですか?一日のスケジュールみたいなものはありますか?
スコット : 基本的には、ツアーで演奏する曲を練習するだけだね。もうGiant Stepsを練習したりはしないよ。気にしなくなったんだ。
スタンダードは一通りやってきたけど、世の中には、僕がどんなに頑張ってもかなわないくらいビバップを上手く弾く人が山ほどいる。彼らに勝とうとも思わないし、目指してるわけでもない。
だから、自分の音楽をやることに集中する。もちろん、自分の曲にもコード進行はあるから、その上で新しいフレージングを探す練習はしているけど、最終的な目的は「自分の音楽を気持ちよく演奏できる状態を作ること」だね。
パット・メセニーが以前、とても深いことを言っていたんだ。「即興を練習するという言葉そのものが、そもそも矛盾している」ってね。
練習というのは、同じことを何度も繰り返すことを意味する。でも即興は、一度も弾いたことのないものをその場で生み出す行為だ。つまり、この2つは本質的に相反しているんだよね。
僕の場合、たとえばコード進行で面白いボイスリーディングを見つけたら、それを使えるように覚えておくことはある。でも、ステージでリックを並べたり、過去に弾いたことのあるフレーズを繰り返したりはしたくないんだ。
パットが言っていたのは、「リックを一切弾かずに練習する」ということだった。つまり、指を想像力に追いつかせる練習。
どんなアイデアを思いついても、それをすぐに指で再現できるようにしておく。それができれば、ステージで新しい音が自然に出てくる。これはリックを練習したり、すでに持ってるアイデアを試したりするのとは正反対のトレーニングなんだ。
ただ、これは本当に難しい。頭の中では「こう弾きたい」と思っても、指がついてこないことがほとんどだからね。でもその練習を続ければ続けるほど、自分のアイデアをそのまま音にできるようになる。そうなれば、即興演奏はどんどん自由になる。練習の大半は、その感覚を鍛えるためにやっているよ。
技術の安定が、創造の自由を生む
—— 曲の練習とソロの練習、どうバランスを取っていますか?
スコット : もちろんソロの練習もするけど、曲をミスなく演奏できるようにすることの方に、より時間をかけている。僕、けっこうミスが多いから(笑)。だから、指に曲をしっかり覚えさせて、頭で考えずに弾けるようにしておく。いわば「自動操縦」状態にするんだ。
ツアーの良いところはそこなんだ。毎晩演奏しているうちに、音楽が自然と手に馴染んでくる。そうなれば、「間違えるな、間違えるな、間違えるな……」と頭の中で唱えながら弾かなくて済む(笑)。代わりに、もっと創造的なことに集中できるようになる。
ステージで「間違えないように」とばかり思っている段階を超えて、「もう何度も演奏してきたから大丈夫だ」と感じられるようになると、やっと音楽を楽しめるようになるんだ。そこからが、本当の意味でクリエイティブになれる。でも、その境地にたどり着くまでには、何本かのライブをこなす必要があるけどね。
恐れを手放して、音に委ねる
—— リーダーとしてやっていく中で、昔と比べて変わったことはありますか?
スコット : 音楽的な変化というより、精神的な変化のほうが大きいね。昔より不安や緊張が減って、ステージでより自然体でいられるようになった。それに、自分の演奏よりもバンド全体のサウンドを意識するようになったんだ。要は、自分のことばかり気にしすぎないこと。なぜなら、自意識が強いほど演奏は悪くなるから。
自分のことを意識しすぎると、演奏中に常に自分をジャッジしてしまう。僕はそういう人の演奏を聴くとすぐに分かるんだ。「あ、この人、自分のことが嫌いなんだな」ってね。
そういう人は同じことを二度と弾かない。何か弾いて、「今のダメだった」と思って、すぐに別のことを弾く。でも次も気に入らない。それを繰り返すうちに、音楽がバラバラになって繋がらなくなる。
だって、自分の出した音を嫌ってたら、何かに集中して弾けるわけがないだろ?そんな状態では演奏に入り込めないんだ。
もし自分の音を受け入れて、「これが今の自分の音なんだ」と認めれば、そこから何かを発展させることができる。モチーフを発展させて、それをきっかけにバンドメンバーと音を交わしながら、一緒に音楽を作り上げられる。
でも自意識が強いと、いつも肩の上に悪魔がいて、弾いたそばから「今の最悪だ」って囁いてくるんだ。まるで自分で自分を裁いて、有罪にして、処刑してるみたいにね(笑)。そんなメンタルのままじゃ、いい演奏なんてできるはずがない。
逆に、自信を持っている人の演奏を聴くと、音そのものから自信が伝わってくる。ミュージシャンでなくても感じ取れると思う。人の話し方から“自信”を感じ取れるように、音からもそれは伝わってくるんだ。同じように、“恐れ”だって聴けば分かる。まるで匂いみたいにね。
だからステージに立って、「間違えたらどうしよう」と怯えていたら、観客にもその空気が伝わってしまう。そんな不安な気持ちのまま弾いていると、ネックに触れるたびに“熱い鉄板”を触っているような気分になるんだ。「あ、しまった」「あぁ、やっちゃった」ってね(笑)。
そうやって自己批判のループに入ると、その夜の演奏はもう下り坂だ。悪循環から抜け出せない。……まあ、これは全部、僕自身の経験から言ってることなんだけどね。今でも、その罠にハマらないように日々意識しているよ。
謙虚さと自信のバランス
—— 先日、ゲイリー・ハズバンドと話したときに、アラン・ホールズワースは人生最高の演奏をした夜でも、ステージを降りると「最悪だった、全然ダメだ」と言っていたそうなんです。
スコット : すごく分かるよ。だって僕も同じだから。ステージを降りた後に「もっと良くできたはずだ」と思わない人なんて、この世に一人もいないと思う。マイケル・ブレッカーでさえ、演奏後に「今日の自分は最悪だった」って言ってたんだ。
でもね、重要なのは、ステージ上の自分とステージを降りた自分はまったくの別人だということ。ステージを降りたら、とにかく謙虚でいるようにしている。自分のプレイにはまだまだ課題があるし、改善すべきところだらけなんだ。
でも、ステージに上がった瞬間に、そんなことは全部忘れる。仲間と音で会話して、思いきり楽しむことだけを考える。
自己批判は、ステージを降りてからやるものだ。ステージの上でそれをやってしまうと、すべてが台無しになる。だからアランが「最悪だった」と言う気持ちはすごく理解できる。僕も毎回そう思うし、ステージを降りたら「もっと良く弾けたのに」って後悔してる。でも、それはほとんどのミュージシャンがそうだと思う。
—— 確かに。
スコット : アーティストは常に「もっと良くできた」と思う生き物なんだ。でもそれは悪いことじゃない。それこそが成長につながるからね。ただし、そこには絶妙なバランスがある。
謙虚であることは大事だけど、ステージ上では自信家でいなきゃいけない。逆に「自分は最高だ」と思い込みすぎると、もう成長できなくなる。だからその中間——自信を持ちつつ、謙虚さを失わない。そのバランスが大事なんだ。
—— まさにその通りですね。
スコット : 僕はアランの気持ちが本当によく分かるけど、その自己批判がステージでの演奏を妨げていたなら、それは残念なことだと思う。実際、彼のライブを何度か観たけど、緊張していて楽しめていない夜があった。でも、リラックスしていて、自然体でプレイしていた夜の彼は本当に素晴らしかった。
これはアランだけじゃなくて、誰にでも言えることだよ。例えばマイケル・ランドウにも良い夜とそうでない夜がある。でも良い夜の彼は、完全に音と一体になっていて、リラックスし、自由で、圧倒的に素晴らしい。
結局のところ、誰でも緊張している夜はうまくいかない。どんなに上手いミュージシャンでもね。
もし自分の中で「ここは少し成長したな」と感じる部分があるとすれば、それは緊張する夜が昔よりずっと減ったということかな。もちろん完璧じゃないし、今でもそういう日がないわけじゃないけどね。
ステージに上がるときは、ただ楽しもうって気持ちでいるんだ。同時に、しっかり聴いて、いいダイナミクスを作って、メロディックでいようとも思う。そして、自分のアイデアを途中で止めずに最後までやり切る。
要は、ステージでは恐れずにいることが大事なんだ。で、ステージを降りたあとに「いやあ、今日もダメだったな」って言えばいい(笑)。
制作と演奏のあいだで
—— 今後、ヨーロッパ・ツアーや新作のプロモーションが控えていると思いますが、それ以外にも予定がありますか?
スコット : 今はとにかくギターを弾く感覚を取り戻しているところなんだ。アルバム制作中は、普段みたいにギターを練習する時間が取れなくてね。
もちろん録音でギターは弾くけど、制作にかける時間のほうがずっと長い。今回もミックスに12日、マスタリング、それにサウンド探し……もう終わりがない。
—— ギターの音だけですか? それともドラムやベースも含めて?
スコット : ほとんどはギターの音作りだね。フレーズを思いついても、ぴったり合うトーンが見つからないことがある。曲の中にしっくり溶け込む音を見つけるまでが本当に大変なんだ。
リスナーには「いい音だな」としか聴こえないかもしれないけど、もし別の選択をしていたら信じられないくらい悪く聞こえていたと思うよ。そのパートに合わない音を選んでしまうと、全体のサウンドが崩れてしまうんだ。
だから、アンプやギター、ペダルを何種類も試して、トラックの中で気持ちよく聴こえる音を見つける。ちゃんと聞こえるけど、出すぎない音。主張しすぎず、かといって埋もれない音。そのちょうどいい加減を見つけるのが本当に難しく、時間がかかるんだ。そのぶんギターを弾く時間は減ってしまうけど、それも制作の一部だと思っている。
正直、ジャズ・ギタリストを羨ましく思う瞬間があるよ。彼らは音作りにここまで悩まなくていい。ギターを手に取ったら、そのまま四六時中弾いていられるんだから(笑)。
時々思うよ。「もしレコードを作っていなかったら、今よりもっとギターが上手くなっていたかも」ってね(笑)
でも、僕はレコーディングそのものが好きなんだ。いわば映画を作るように、音を積み重ねてひとつの大きな物語を作り上げていく。その過程も、作曲やプロデュースの作業も、僕にとってはすごく刺激的で面白い。
だから今は、完全に“プレイヤー・モード”に戻ってる。1日中ギターを手にして、感覚を取り戻すことに集中してるよ。レコーディングが終わった直後は、「あれ? ギターってどう弾くんだっけ?」って感じるくらい鈍っているからね(笑)。
プレイヤーとしての現在地
—— 今でもギターと向き合い続ける姿勢、本当に素晴らしいです。
スコット : ギタリストは、常にテクニックを維持しておく必要があると思っている。とくに大事なのは正確さだね。ギターを弾くうえで最も重要なのは、ミスをしないことなんだ。
たとえば、弦をピッキングする瞬間に指の動きがほんの少しズレると、音がちゃんと出なかったりする。テンポが速くなるほど、その正確さを保つのが難しくなるんだ。
僕が言うテクニックは、いわゆる速弾きのことじゃないよ。世の中には僕の10倍速く弾けるギタリストが山ほどいるし、そこを競っても意味がないと思っている。
僕が意識しているのは、その瞬間に思いついたアイデアを、ミスなく形にできるかどうかなんだ。つまり、頭の中で思いついたフレーズを、そのままスムーズに音にできるかどうか。そこに致命的なミスがないか。そういう演奏をするためには、体とギターとひとつになっている感覚が欠かせない。
だからこそ、いつもギターを手にしていることが大事なんだ。少しでも弾かない日があると、すぐに感覚が鈍ってしまう。朝起きてギターを手に取ると、まず思うんだ。「うわ、弾き方忘れたんじゃないか?」ってね。
でも、何時間か練習しているうちに、少しずつ感覚が戻ってくる。「ああ、形になってきたな」と思えて、自信も出てくるし、ミスも減っていく。そうやって毎日少しずつ、確実に良くなっていくんだ。
だから、ツアーが始まる2月の中旬までの間、毎日練習して感覚を完全に取り戻そうと思ってる。そうすれば、ツアーに出る頃には「よし、これで準備万端だ」って思えるはずさ。
音楽を“自分の手”で届ける
—— 次のアルバムもご自身のレーベルから出す予定ですか?
スコット : うん、そうだね。もうレーベルに頼るつもりはないんだ。
—— どうしてその決断に?
スコット : きっかけは、レコード会社のマイク・ヴァーニーの助言だった。彼はただのレーベル担当じゃなくて、昔からの親しい友人でね。
『Vibe Station』を作っていたとき、彼はすでに7〜8千ドルを制作費として出してくれていたんだ。でもその途中で、彼が手がけた作品の権利をまるごとSonyに売却することになって。彼が僕に言ったんだ。「このまま進めると、新作の権利がSonyに移る」って。そうなったら大変だよ。あんな巨大な会社じゃ、きっと僕は相手にされないだろう。それだけは何としても避けたかった。
それで彼が提案してくれたんだ。「残りは自分で出資して、自主リリースしたらどうだ?今はCD Babyやインディ系の流通会社もあるし、中間業者を通さずに自分の手で届けられる時代だよ」って。
もちろん、その分やることは増える。ミュージシャンへのギャラ、スタジオ代、デザインや印刷費、広報費、すべて自分持ち。流通会社への発送費までね。だから手間もコストもかかるけど、やってみたら「全部自分でやる価値がある」って思えたんだ。
実際、売り上げはすべて自分に入るし、レーベルに取られることもない。だから経済的にもやりがいがあるし、この方法を選んで本当によかったと思ってる。もう、他の手段を取る気にはなれないね。
今回のアルバム制作には、だいたい2万3500ドルかかった。全部、自腹だよ。確かに大金だけど、時間をかければ回収できると思ってるし、その利益でまた次の作品を作れる。だから、もうレーベルに戻るつもりはないんだ。
もちろん、新人のアーティストなら話は別だよ。まだ資金の余裕がなくて制作費を用意できないなら、レーベルに出してもらうのも悪くない。たとえ大きな利益は望めなくても、自分の音楽を世に出せるという意味では、とても価値があることだからね。
でも僕みたいに、ある程度経験を積んだ立場だと、もうレーベルに頼る理由はない。結局のところ、自分がどんな状況にいるか、それ次第なんだ。
アメフト雑談
—— 今日は貴重なお話を伺えて光栄でした。お時間をいただき、ありがとうございました。
スコット : こちらこそ、ありがとう。
—— ところで、今かぶってるそのキャップ、すごくいいですね。
スコット : ああ、これ?(笑)僕はロサンゼルス・ラムズを応援してるんだ。今シーズンは3連勝中で、明日はボルチモア・レイブズ戦なんだよ。
—— でもサンフランシスコが今年は勝つと思いますよ(笑)。
スコット : まあ、ラムズにはあまり期待しすぎないようにしておくよ(笑)。
—— 僕はどちらかというと、バスケットボール派なんですよ。お気に入りのチームのパーカーをたくさん持ってて。
スコット : ああ、いいね!僕もバスケは好きだよ。でも、どちらかというとフットボールの方が好きなんだ。もうずっと昔から。
特にラムズとマイアミ・ドルフィンズを応援してる。今年のドルフィンズは本当に調子がいいんだ。ここ何年もこんなに良いシーズンはなかった。それに、僕はマイアミ出身だからね。応援しないわけにはいかないんだ(笑)。
Samo SalamonのYouTubeチャンネル
今回のインタビュー動画を公開しているのは、スロベニア出身のギタリスト、Samo Salamon(サモ・サラモン)さんのYouTubeチャンネルです。
ジャズギタリストへの深いリスペクトと鋭い洞察にあふれた内容で、見ごたえのあるインタビューばかり。
ぜひチャンネルでチェックしてみてください。

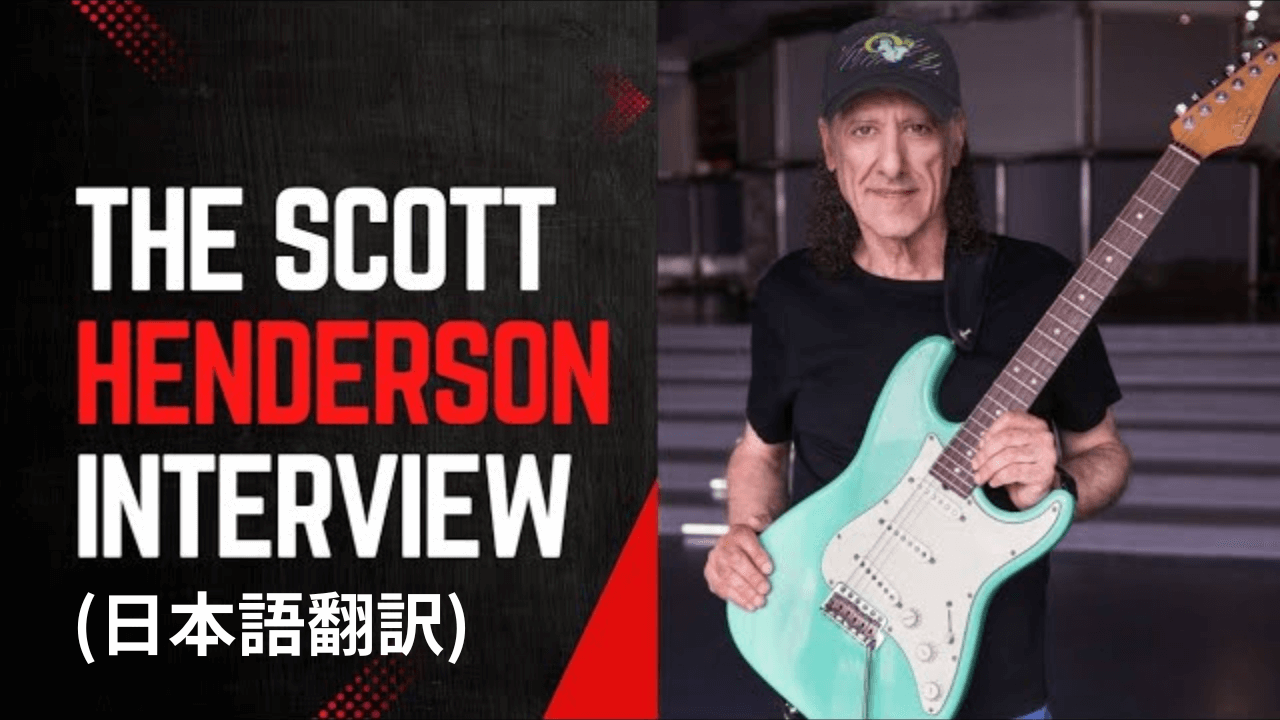



![ABRAXAS [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/618CJRU5ugL._SL160_.jpg)
![CARAVANSERAI [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SYFhvVfSL._SL160_.jpg)


